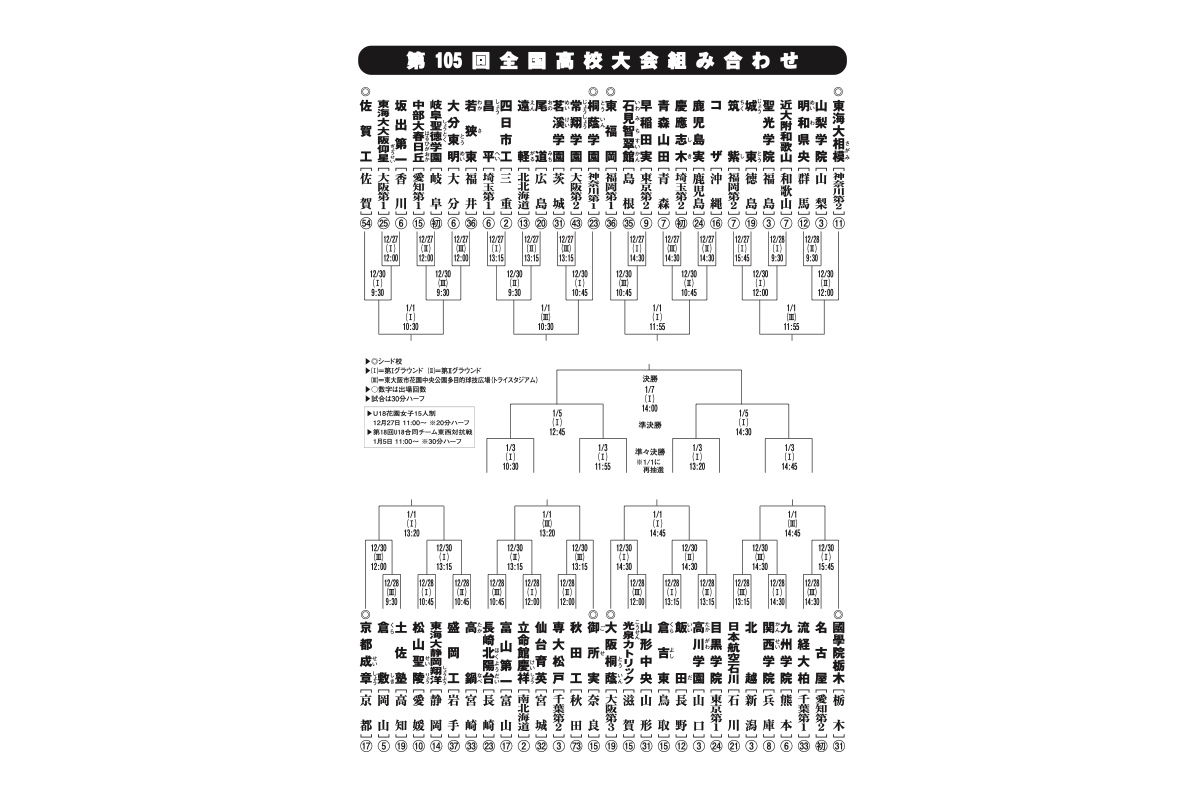【コラム】サイズを超えて。
2019年のザ・ラグビーチャンピオンシップにも出場しているヘモポだが、当時の代表チームでの立ち位置は「シニアメンバーにケガ人が出たら代わって入るというレベル」(本人談)だった。レギュラー定着の障壁となったのがサイズである。膠着した局面を打開する突破役としては不足とされた。
195センチ、112キロの偉丈夫に「スモール」の表現がふさわしいかはさておき、いまや国際級のLOといえば2メートル、120キロがアベレージサイズだ。ヘモポが小柄な部類に入るのは確かだろう。そのためコーチからは常に「もっと体重を増やせ」といわれ続けてきた。しかしどれほど栄養管理を徹底し、厳しいトレーニングを重ねても、思うように目方は伸びない。
「小さい頃から背は高いけれど軽かった。そういう体質なのです。どうやっても重くなれない。悩みました」
そんなヘモポを救ったのが、ハイランダーズ時代にも指導を受け、今季からダイナボアーズのヘッドコーチに就任したグレン・ディレーニーだった。同じLOであり、ニュージーランドの高校を卒業後、19歳で来日してトーヨコで社員として働きながら3年半プレーした経験を持つディレーニーは、悩むヘモポにこう言葉をかけたという。
「無理に重くなる必要はない。重い選手と同じぐらい激しくプレーしてくれれば、体重が何キロかなど誰も気にしなくなる」
大切なのはパフォーマンスの質と量であって、体格は劣ったとしてもプレーで上回ればそれでいい。そういわれて燃えないラグビー選手はいない。もちろんジャックスも燃えた。
激しい身体接触をともなうラグビーにおいてサイズの威力は絶大だ。大と小が真正面からぶつかれば、大きいほうが前に出る。ただし「必ず勝つ」とは限らない。そこに、心技体のさまざまな要素によって構成されるこの競技の醍醐味がある。
身長が低くても、体重が軽くても、多少の差ならクレバーさや激しさで互角以上に対抗できる。コーネルセンやヘモポはそれを体現する存在だ(とはいえ十分大男だが)。もしかしたら小よく大を制す戦いが前提の日本ラグビーのエッセンスに触れたことが、体内に宿る潜在力を引き出し開花させた部分もあるかもしれない。近年のジャパンの国際舞台における躍進を見ると、それもあながち身びいきな思い込みではないように感じる。
最後に。創意と工夫とたゆまぬ努力で体格差を克服し、偉大な足跡を残した元日本代表の言葉を紹介したい。
横井章。165センチ、58キロの身体でCTBを持ち場とし、いまよりずっとテストマッチの機会が少なかった1960年代後半から70年代中盤にかけて17キャップを獲得した。1968年にオールブラックスジュニアを破った日本代表の主軸であり、1970年から74年まではキャプテンも務めている。
今年5月に発刊された著書、『継承と創造』に編集協力として携わった際の取材の中で、近年多くの高校チームが頭を悩ませる部員不足の話題になった。大手前高校時代はバスケットボール部に所属、1年の受験浪人を経て入学した早稲田大学でラグビーを始め、同年秋には1軍で公式戦出場を果たした伝説の人物はいった。
「ラグビーはコンタクトスポーツやから、指導者はどうしても体の大きい子に目が行く。でも、大きい選手や運動能力の高い子ばっかり探そうとするから、意欲があって痛さや怖さを克服できる可能性を秘めた子に目が向かない。それが、なかなか人が集まらない状況を招いているんやないかと感じますね」
2000年以降の20年あまりで全国100校以上の高校、大学でスポット指導にあたってきた現役コーチが何気なく発したひと言。これ、金言ではないか。