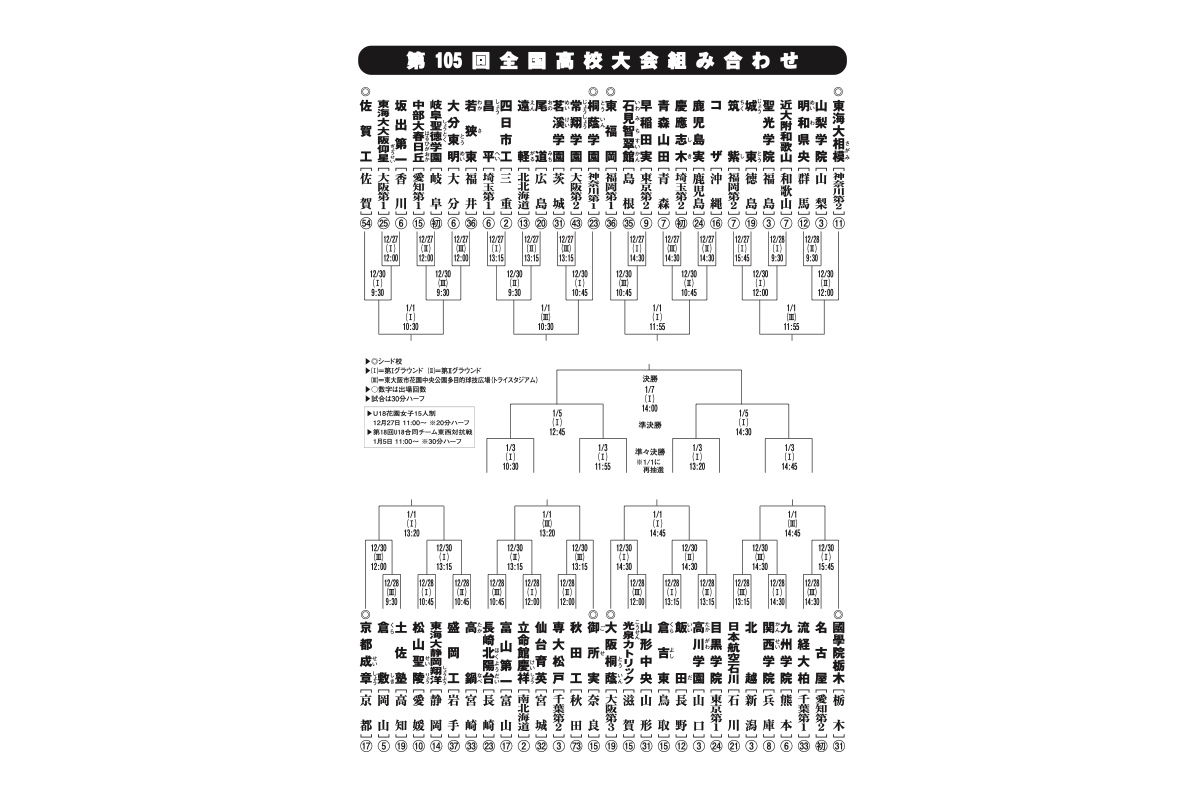【ラグリパWest】道を譲る。南屋大 [私立甲南高校・中学校/保健・体育教員/ラグビー部前監督]
![【ラグリパWest】道を譲る。南屋大 [私立甲南高校・中学校/保健・体育教員/ラグビー部前監督]](https://rugby-rp.com/wp-content/uploads/2025/05/PXL_20250425_075155919.MP3.jpg)
そのグラウンドは南に向かって右をラグビー、左をサッカーが使う。奥には野球の黒土。左の彼方には大阪湾が白く光る。
甲南高校・中学校は兵庫・芦屋の山の手にある。南屋大(みなみや・だい)はこのグラウンドを右から左に移った。
24年間、ラグビー部の監督だった。
「ほぼひとりでやってきました」
その道を後進に譲る。4月1日からサッカー部の顧問に変わった。
大きく澄んだ双眸は穏やかだ。
「学校のためを考えると、僕が退くことが最善だと考えました」
赤銅色の肌は保健・体育教員を示す。
甲南高校・中学校はほぼ一貫校だ。短く「甲南」で通る。灘、甲陽学院、六甲学院の4校で阪神間の名門私立男子校を形成する。
その甲南は新年度、ラグビーを専門にする保健・体育の正教員を迎えた。櫟原(いちはら)雄樹。37歳。福岡・光陵から大阪体育大に進んだ。現役時代はWTBだった。
南屋は52歳。ラグビーの経験はない。教員免許を取った中京大では合気道をやった。二段を得る。講師の4年間はバスケットボール部の顧問。正教員になった2001年からラグビー部に携わり、同時に監督になる。
甲南の保健・体育の正教員は5人いる。
「専門の競技というよりも、教員として優秀な人を採用する傾向があります」
サッカーの監督だった半田篤が65歳定年になり、その補充を公募する。決まったのがここで講師経験のあった櫟原だった。
「ただ、5人で2人がラグビーというのはバランスがよくないですよね」
南屋は自分の意志で身を引いた。
とはいえ、これまで南屋が<名前だけ監督>だった訳ではない。冬の全国大会県予選でこれまで4回の決勝進出がある。そのうち半分の2回は南屋が成し遂げている。
ともに決勝の相手は報徳学園。84回大会は24-53。88回大会(2008年度)は11-14だった。2回目は3点差の惜敗である。
「全国大会に出たかったなあ」
南屋は笑った。
「試験的にモールをつぶす行為が許された年でした。1年でなくなりましたけど」
ルールを研究して初出場に迫った。
「競技歴があるかどうかというのは、コーチにとって関係ない。大切なのは選手たちのモチベーションをどう持たすかなんやな」
亡き平尾誠二は語ったことがある。平尾は男ぶり、賢さ、魅せるプレーから「ミスターラグビー」と呼ばれた。その言葉を引けば、南屋は疑いなく有能である。
渡邊雅哉は南屋の一報を聞いた。
「残念です」
渡邊は芦屋のラグビー部監督である。同じ市内にある県立高校だ。そのいわばライバルからも惜別の言葉が出る。
甲南の創部は旧制中学時代の1924年(大正13)。昨年、100周年を迎えた。県内では最古だ。ジャージーはエンジに胸に白一本ライン。主なOBは松岡大和。S愛知のFW第三列で、天理大時代は主将として初の大学選手権制覇を達成する。57回大会(2020年度)の決勝は早大に55-28だった。
旧制中学の創立は創部の5年前。これは大学、高校、中学校を統べる学校法人「甲南学園」の嚆矢(こうし)となった。創立者は政財界の大立者、平生釟三郎(ひらお・はちさぶろう)。文部大臣や川崎造船所(現・川崎重工)の社長をつとめた。
平生はフェアプレーのラグビーを好んだという。三男の三郎は旧制の甲南高校から京大に進み、CTBとして日本代表キャップ2を持った。1932年(昭和7)、カナダ代表との2試合に出場。9-8、38-5と連勝した。
今の在校生は高校で約200人、中学校で180人ほどだ。南屋は説明する。
「25人くらいが高校から入学します」
高校は普通科2コース5クラス制。アドバンストが3クラス。甲南大への進学が中心だ。フロントランナーは2クラス。医学部や他大学受験を目指す。
南屋の着任は1997年。その前は武庫工(現・武庫荘総合)に2年いた。武庫工の竹本純一が甲南教頭の樋口英雄に紹介する。
「君はよい眼をしているなあ」
初見でそう言われ、非常勤講師になる。
樋口も保健・体育出身だった。神戸大では陸上を専門にしたにもかかわらず、バスケットボールの顧問になった。
「樋口先生はインターハイに出しました」
南屋はその歩みを見て、勇気づけられる。それはまた、平尾の言葉の裏づけになる。
樋口が16代目の校長になったのは2000年。翌年、南屋は正教員に引き上げられる。
「なんのとりえもないのに、色んな人たちに助けてもらって、ここまで来ました」
感謝が口から出る。それは他競技の時代も含める。中学はバレーボール、高校は軟式野球をやった。県立校の鳴尾(なるお)である。
中京大で合気道を選んだ理由がある。
「消防士や警察官になりたかったので、そのための護身術的な感じでした」
その志望が大学4年で変わる。母校の鳴尾での教育実習の時だった。
3週間、後輩たちと接した。
「パソコンが普及していない時代で、指導案は下書きをして清書。寝られませんでした」
校内での作業は指導教員に止められた。
「そんな時間があるなら、生徒と関われ」
付き合いが深くなれば、後輩たちの初々しい可愛さが伝わる。志望を教員に変更した。
そして、武庫工を経て、甲南にやって来る。ラグビーからサッカーに顧問を変える。その新しい保護者会が4月26日にあった。
<みなさん喜んでくれました>
メッセージからは歓迎の意が伝わる。
「生徒を育てる。同じことをやるだけです」
南屋の両目は亡き樋口がほめたように慈愛に満ちた光を放っていた。
南屋は離れゆくラグビーのよさを語る。
「痛みを伴うのに、人を助けることをあえてやる。それをチームとしてやることです」
自己犠牲。社会に出てからも大切な生きざまである。今回の一連の流れを見れば、その精神は南屋にもまた備わっている。
![プレーオフかけた大一番に臨む松島幸太朗[東京サンゴリアス/FB]、「良い雰囲気」..](https://rugby-rp.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG_1092-272x153.jpg)