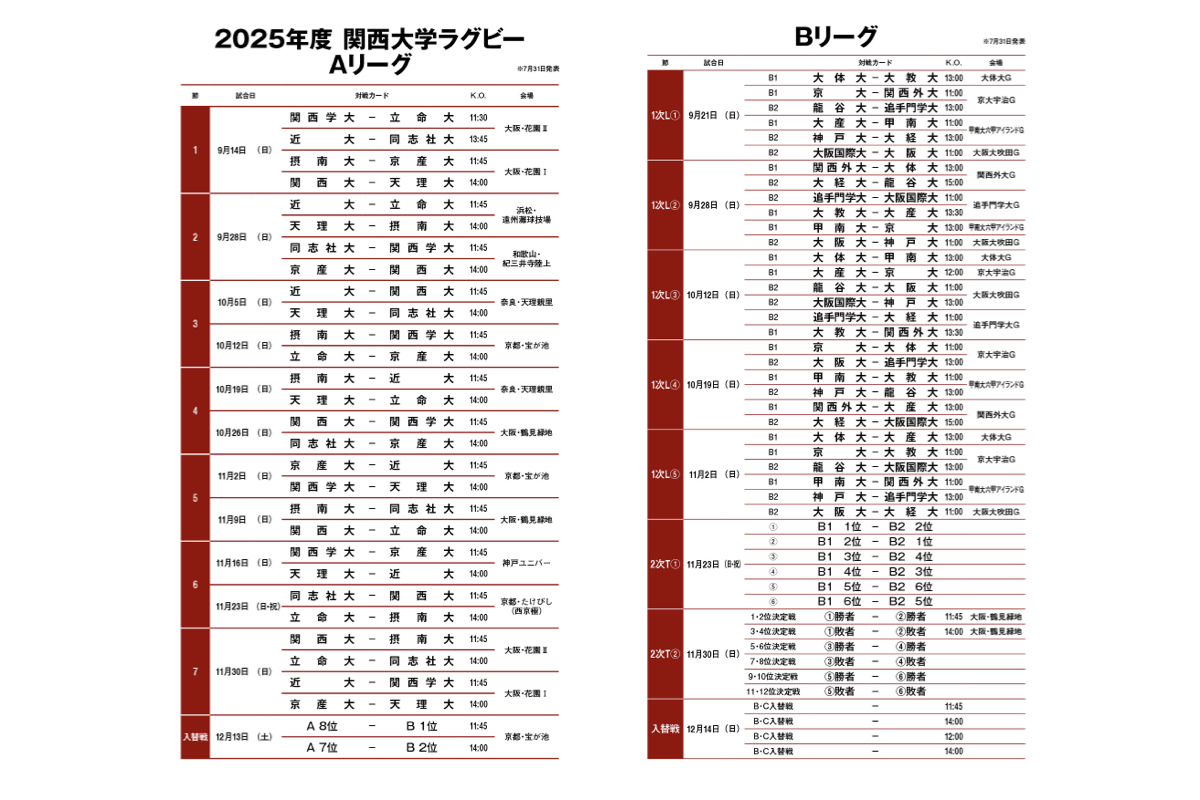【コラム】スクラムが分からない。

2023年からエンタメ企業などの不祥事が相次いでいる。ラグビー界もいよいよ黙認こそがリスクであるとマインドセットを変えつつ、業界内のあたりまえを総点検する必要があるだろう。あの大帝国ジャニーズの凋落から読み解けるメッセージは、「すべては起こりうる」ということだ。文春砲ならすでに経験済みのラグビー界だが、今後BBC砲を食らう可能性がないとも限らない。
隗より始めよということで、まず筆者がラグビー界のおかしな点を探してみたら、すぐに当たり前のように存在している「アレ」のおかしさに気がついた。プレーや現象に与えられている名前・ラベルを全部忘れてラグビーを眺めれば、誰もがそのおかしさに気付くはずだ。
そう、スクラムである。
人類滅亡後の次に登場した高度な知的生命体が、ヒトが生きていた世代の地層から奇妙な痕跡を見つける。彼らも「スパイクと呼ばれていた履き物の跡」までは辿り着くかもしれない。しかしそれがスクラムを組んだ跡だと分かることはないだろう。
あらためて奇妙だ。ボールゲームの中に8対8で押し合う競技がビルドインされている。そして筆者はその別競技「スクラム」について、何故いつまでもまったく理解できないのだろうか。筆者がスクラムに関して確実に言えることは、閉所恐怖症ではフロントローは務まらないだろうということくらいだ。
もうひとつ言えることがあった。「スクラムで負けている方の見分け方」だ。これは簡単で、バックスのノックオンに平然としている方が勝っている方で、ノックオンをしたバックスを睨んでいるのが負けている方だ。
この程度のことしか言えない筆者は、長きにわたり、スクラムについて理解できないライターが自分だけでなければいいが、と怯えていた。しかし味方は意外なところにいた。ラグビーW杯を振り返る日本代表戦DVDのコメンタリーで、日本代表のバックス選手が「スクラムは分からない」と話していたのだ。
そういえばオーストラリア代表の名フルバックも仲間だった。2017年、緊急でフランカーとしてスクラムにつくことになったオーストラリア代表FBカートリー・ビールは、ひとしきり狼狽した後、最終的にプロップではなくロックのお尻を押していた。
それを観て天にも昇る安堵感を覚えたのだが、考えてみれば代表クラスでさえ分からないものが、突然始まること自体に問題はないだろうか。演者の理解できない「劇中劇」が突然に始まり、全体の流れを変えてしまったりするのである。たとえば2019年W杯アイルランド戦前半35分のスクラムがそうだった。
もともと黎明期のスクラムは、19世紀イングランドでは5、60人が参加する大規模な押しくらまんじゅうだったという。その目的は「プレー再開」ではなく「ボールを相手側に向かって蹴ること」。1967年の試合映像でさえ粗暴だった時代のスクラムの面影がある。
スクラムがいまだ押しくらまんじゅうだったら筆者が「理解ができない」と悩むこともなかったはずだが、安全性確保から厳密化していったルールによって、スクラムは「別競技のよう」に感じられるまでに高度化してしまった。
深化したスクラム世界は恐ろしい沼でもある。バックローをフロントローに転向させるコンバートの一大潮流があるが、スクラム世界に旅立った者が戻ってくることはまずない。BBCに拉致疑惑として目を付けられることはないはずだが、沼にはまってチーム・大会関係者となったフロントロー出身者のなんと多いことか。
逆をいえばそれだけの魅力があるということなのだろう。
オークランド(ニュージーランド)で、押し合わないスクラムを採用してきた13人制ラグビーを観戦したことがある。激しい正面衝突と華々しいボール展開で構成されるゲームは、観客を興奮させる装置として優れていたが、観客は興奮させられるだけだった。15人制の観客席にあるような、プレーを理解しようとする、意図を汲み取ろうとする姿勢、間がないように感じられた。
考えてみれば、理解できない領域がある、理解できない人びとがいるということは、常に学ぶ機会を与えられているようなもので素敵である。理解しようとする姿勢を与えてくれるスクラムに感謝しつつ、今週末もおそらく理解できないであろうスクラムと向き合いたい。