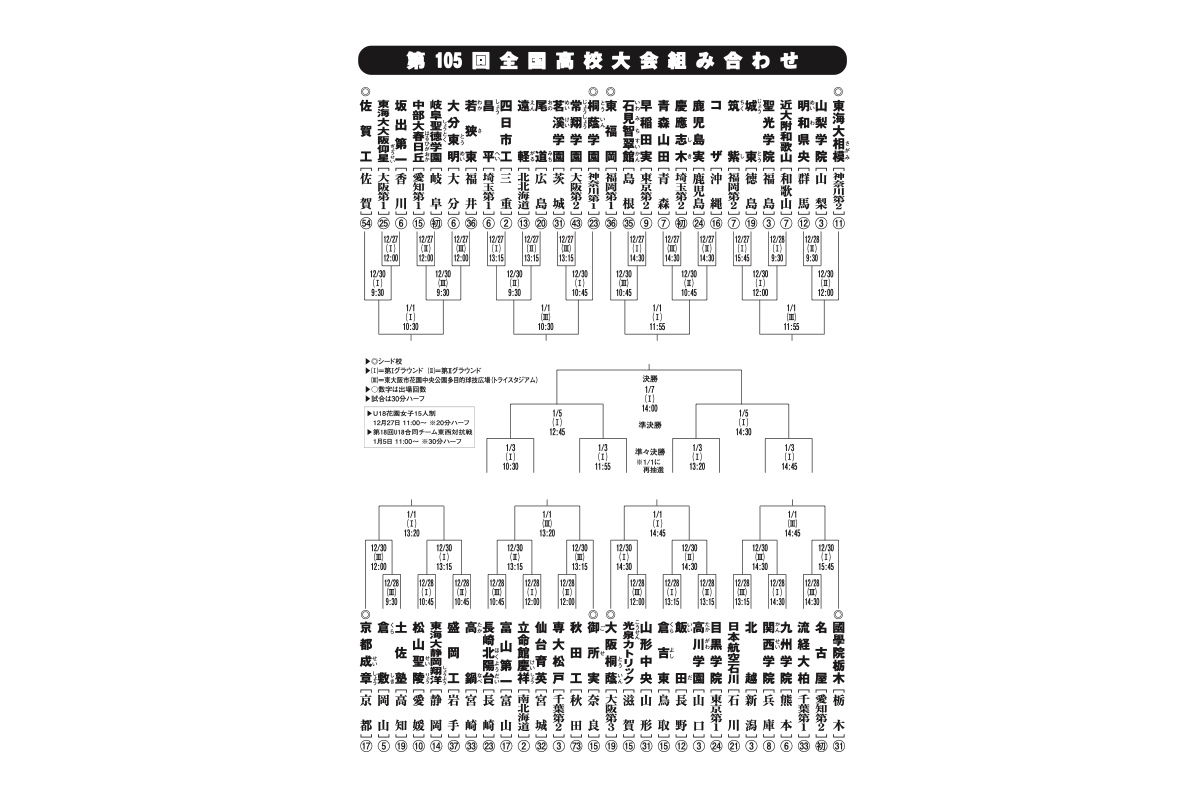【コラム】99回目の定期戦。ジャージーに滲むチームの色。
昨年の定期戦の場面に戻る。東大は後半38分、ラインアウトモールからのトライでスコアを15―5とした。
残り時間が僅かとなった中、京大が敵陣のゴール前左でスクラムを組んだ。何とかボールを確保したSH野澤朋仁が2人のタックルを受けそうになる。瞬間、後ろにボールを投げる。このプレーに味があった。楕円球が転がったのは無人の芝の上。WTB加清渓太が戻りながら拾い上げると、野澤が2人を引き付けたおかげで目の前が空いていた。再び5点差に迫るトライ。
後半42分には、めまぐるしく攻守が入れ替わる中、京大が中盤右でラックをつくった。タッチラインまでの距離は10メートル。この幅なら攻守ともにブラインドサイドに残す人数は1人か2人だろう。しかし、京大はなぜか4人が肩をぶつけるように並んでいた。
選手の機転か、オープンサイドに回る力が残っていなかったのか。偶発的にできたように見えた、狭いスペースの4対2を京大は見逃さなかった。SH野澤が自ら持ち出して突破すると、CTB水野武主将につないでトライ。ゴールも決まり、土壇場で17―15と試合をひっくり返した。
ラストプレーになりそうなキックオフ。東大は深く蹴る。京大のロングキックをキャッチしてボールを取り戻すと、最後の攻撃を始めた。鋭いタックルで押し戻されるが、相手が勢い余って倒れ込んでしまう。追う側にとって、喉から手が出るほど欲しいペナルティー。4本目となるラインアウトモールからのトライは、試合を決める得点となった。
通算99回目となる定期戦は、ホームチームの劇的な勝利で終わった。ただ、信じた道を貫く東大、柔軟な判断で抵抗する京大という対比は、何度も繰り返されてきた光景だったかもしれない。
蛇足として、両校のチームカラーの話をもう少しだけ。筆者の現役時代の経験や、その後に見た試合、耳にした談話という限定された情報からの私見です。
東大はチームの根本となる方針、戦略の部分で王道を行く。ラグビーの土台であるFWを鍛え、タックルを磨く。保守本流とも言える道に向かい、チームの意思が統一されている。その一方、戦略を実現するための戦術のレベルでは様々な工夫が凝らされている。
15年ほど前、東大OBが多く所属するクラブチームの試合を訪問、ウォーミングアップに参加したことがある。メニューの1つが、流れの中で用いるサインプレーのおさらいだった。6人ほどがランダムに位置に付き、複雑なムーブを繰り出す。これが十数種類も用意されていた。元ネタは一時期の東大で使われていたサインプレーだと聞いた。「全部を覚えて試合で使うなんて、さすが東大だな」。一緒に参加した友人が舌を巻いていた。
不発に終わった「タップキックからの突進」も、インゴールでグラウンディングできないリスクと、ラインアウトでボールを失う危険性を天秤に掛けた上での判断だったのだろう。
対照的に、京大は時代によってこだわりが変わる。コンセプトや戦略の次元にまで手を加える。良く言えば柔軟、悪く言えば一貫性がない。選手一人ひとりが良く声を上げることもあり、まとまりでは東大に及ばないかもしれない。しかし、時には「革新」が生まれる。
2001~02年は市口監督の発案による独自の戦法を採用していた。選手をフィールドに満遍なく配置、ボールを大きく動かすという点で、現在流行の「ポッド」と呼ばれる戦術を先取りするようなモデルだった。セットプレーの後はSH以外の14人がまったく同じ役割をするという点で、よりラディカルとも言える。少なくともその2年間は、対応に面食らう相手から多くのトライを奪うことができた。
1926年の大正天皇崩御、1944年の太平洋戦争激化、2020年の新型コロナウイルス禍――。3度の中止を除き、毎年行われてきた定期戦。99回目の対戦にも、過去と同じような対照の妙があった。
◆試合の動画はこちら