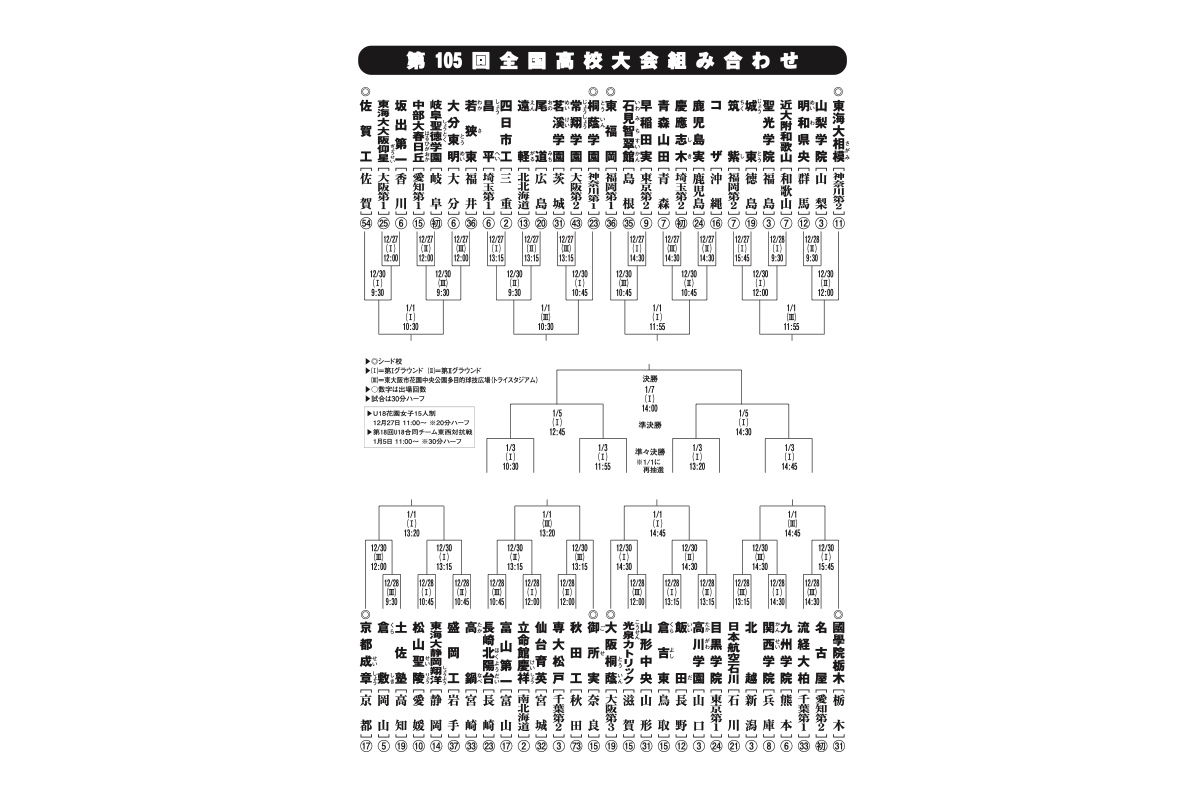【コラム】実行と肌感覚。適応のシーズン
2年生の大賀宗志は「外出したい気持ちもあるんですが、4年生がルールを守っているのだから」と先輩方を尊敬する。2018年度に22年ぶり13回目の日本一に輝いた明大は、カレッジスポーツにおける4年生の影響力を重んじる。
熱が高まったのは11月1日。参戦先の関東大学対抗戦Aで慶大に12―13と敗れたためだ。エリアごとのプレー選択を見直しただけでなく、競技力以外の側面からも反省点を抽出した。
スタッフがトレーナールームのかすかな乱れを「これが日本一を目指すチームのそれだろうか」との旨で指摘し、主将の箸本龍雅は「それを自分で気付けなかった」と恥じた。以降、4年生だけで練習後の道具を片づけるようになった。
わずかな、しかし確かな変化について、田中澄憲監督は「本格的なキャンペーンが始まった」。どこか、悠然と構えていた。
もしや、「トレーナールーム」の件をもっと前に気づいていながらあえて放置していたのか…。
「もちろん。どこで(伝えたら)響くかっていうのは、あるじゃないですか」
場所は八幡山のグラウンド。2017年にヘッドコーチとして入閣してグラウンド内外の規律を正した元代表選手は、落ちかけた陽を向こうに滔々と述べるのだった。
「ただ、(敗戦を受けて気づかせたのは)策略でも何でもなくて、いまやらなきゃ…というところです。学生って、たぶんこの(凡事徹底を再確認する)繰り返しだと思うんです。学生スポーツらしくて、いいんじゃないですか」
12月6日の秩父宮で早大との対抗戦最終節を34―14と制し、日大戦から14日後の秩父宮(準決勝)で、2020年度の、ピリオドを打った。8月中旬には部内でクラスター発生の天理大に、15―41と圧倒された。
2年連続で日本一を逃したのは名門にとって屈辱だろう。それでも例の「キャンペーン」が最後まで続いたことは、誇れるのではないか。
あの日の田中は、こうも言っていた。
「コロナのなかで、がんじがらめになっているわけじゃないですか。そこで僕も、言い過ぎ、やらせ過ぎは可哀そうかな思っていたんです。だけど、(トレーナールームの件を受けて)甘かった。僕も、学生たちも、気づきながら、経験しながら、成長していくんです」
厳しい現実に直面した時、人はその出来事を前向きに捉えようとする。その方が建設的だからだ。
その延長で、アスリートは難局を乗り越えて結果を残せば「あれがあってよかった」と述懐する。今季の大学ラグビーシーンに挑んだ学生、指導者が「この状況で試合ができることに感謝します」と公式に発したのも、自然な流れである。いずれも本心だろう。
ただし、この点も見落とせまい。
いくらウイルス禍と逞しく向き合う若者の声が聞こえてきたとしても、すべての若者がウイルス禍を本当の本当に「あれがあってよかった」と考えているとは限らない。
エネルギーの有り余る20歳前後の青年がつかの間のオフに地元へ戻るのも憚られ、試合後に飲みに行けば戦犯扱いされかねなかったのだ。これを「好きなことをやっているのなら多少は我慢すべき」と断言できる聖人君子は、そう滅多にいないはずだ。そもそも万人の生命を狂わせうる新型コロナウイルスなど、あってよかったわけがない。
2020年度シーズンのすべてのラグビーマンは、踏ん張ることの難しさと尊さをその人だけの皮膚感覚で掴み取った。その姿が綺麗なのだとしたら、各々の背景が「綺麗ごと」だけではなかったからだ。