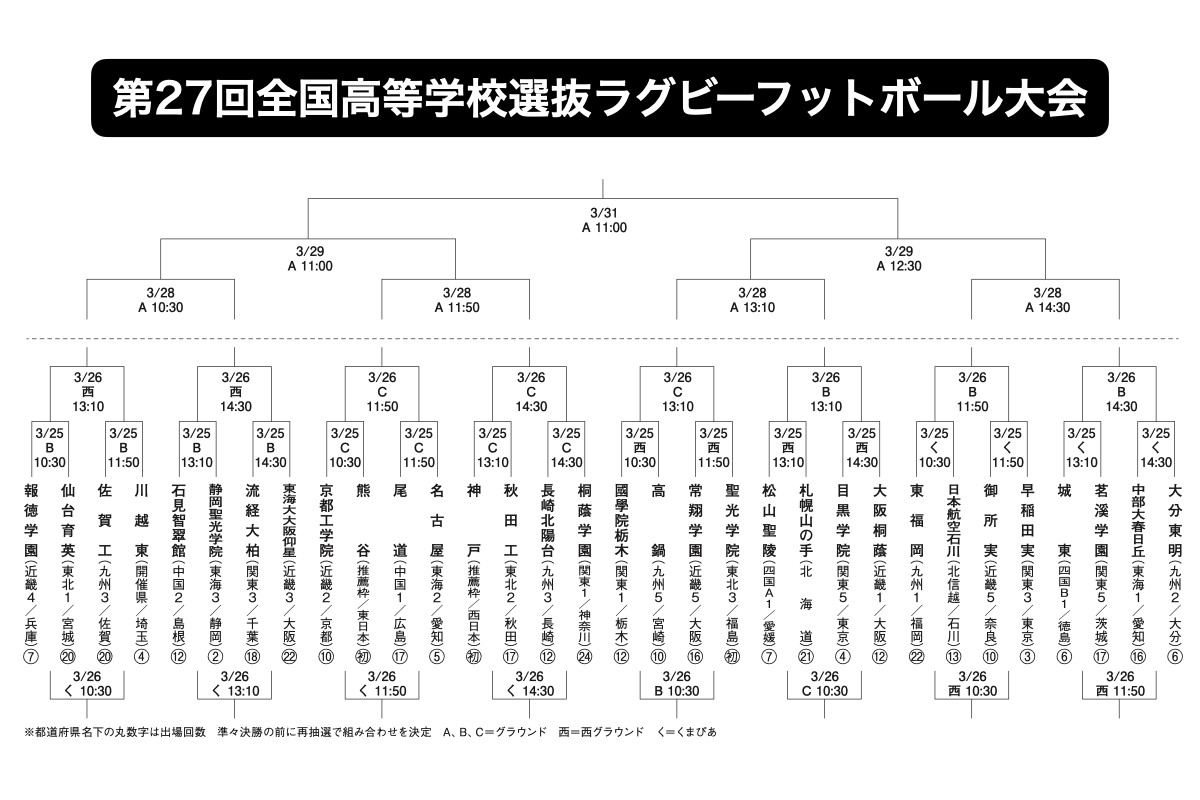![【再録・ジャパン_06】中村亮土[2013年10月号/解体心書]](https://rugby-rp.com/wp-content/uploads/2020/07/06_2013_10ryoto__bl.png)
【再録・ジャパン_06】中村亮土[2013年10月号/解体心書]
「大学では、基本的に判断するスペースを持つために深めに立っていますが、チャンスが来たらどんどん前に出ていきたいですね」
ジャパンで得たものを積極的に帝京ラグビーに持ち込み、自分と仲間の連携を深めようと思っている。
ジャパン招集以来、もっとも徹底されたのは、『コミュニケーション』のことだった。「誰でもできることです。ただ、求められたレベルは簡単ではなかった」と振り返る。
パスひとつにしても、黙ってもらうのと、「いま」「ここ」と伝えるのでは大きく違う。自分のことを伝える。相手の声を聞く。FWが動きやすいように指示を与え、周囲を動かしておいて自分が動く。それらを意識して声を出したつもりでも、エディー・ジョーンズ ヘッドコーチには「それでは大学レベルでしかない」と高いクオリティーを求められた。
「でも、最初は何を言われているのかすら分からなかったのが、少しずつ理解できるようになりました」
相手がUAE(5月10日/93―3)とはいえ、この春、テストマッチ出場の機会を得た。決して妥協しないチームだ。指揮官が、一定のレベルに達したと認めた証しだった。
やっと巡ってきた初キャップ獲得の達成感は、思っていた以上に自信となった。相手とのレベルの違いは分かっている。ただ、勝って当たり前という雰囲気の中で結果を残す。この国のラグビーマンたちの代表として桜のエンブレムを胸に戦う。そういう重みに身が引き締まった。
前半35分、ベンチから飛び出た。その瞬間を忘れない。出場直後に走った。回ってきたボールを手にすると、思い切って自ら前に出る。ビッグゲインだった。
「ファーストタッチから行こうと思っていたんです。周囲の先輩たちも、『いけいけ』という感じだったので。あの試合、とにかくやれることはすべて全力でやろうと思っていた。とにかくボールにたくさん触りたかったから、どんどんブレイクダウンにも入った。ひとつのプレーが終わったら急いでリポジション。プレーの善し悪しに関係なく、日本を代表して戦えたことが大きかった。『あの場』で得られるものは、あそこにしかないものでした」