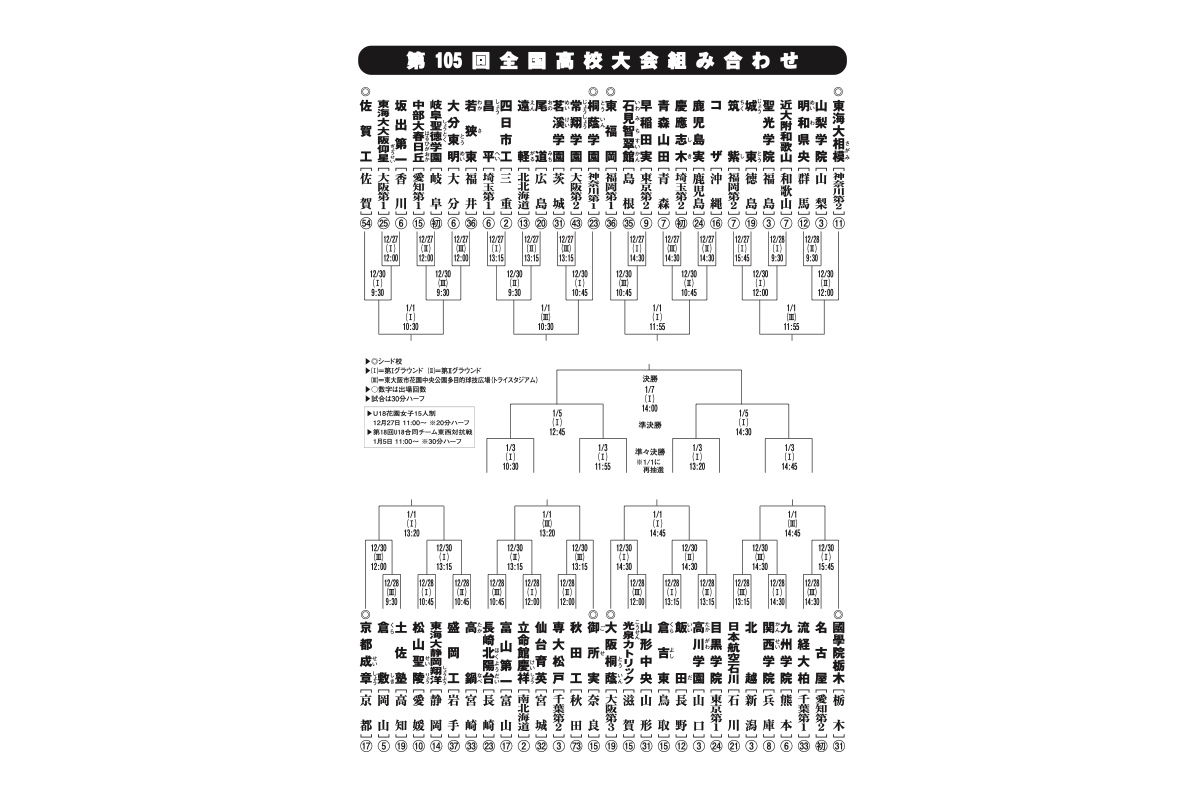【村上晃一の楕円球ダイアリー#3】「こんなに面白いポジションありませんよ」

スクラムからボールが出てくるからこそ、ラグビーは面白い。
フランス語の通訳者であり、ライターでもある福本美由紀さんにインタビューしたことがある。
福本さんは、フランスのラグビーをこよなく愛する人だ。フランスラグビーと言えば、スクラムに並々ならぬ探求心があることで知られている。
「ラグビー経験のある哲学者が、スクラムはマトリクスだと言っていました。つまり母体です」
マトリクスという言葉は、「子宮」を意味するラテン語から来ているそうだ。つまり、ラグビーのボールはスクラムから生み出されているということ。深く共感した。
だからこそ、ボールには血が通い、そのボールが大切につながれていく様子に観る者は惹きつけられる。
スクラムから出たボールと、他の起点から出たボールに重みの違いを感じるのは筆者だけではないだろう。
筆者は小学5年生からラグビーを始めた。ポジションは主にバックス。練習でスクラムを組むことはあったが、公式戦で組んだことはないし、遠くから眺めることが多かった。
それでもスクラムの大切さは痛感している。味方が押されるとオフサイドラインが押し下げられるので、バックスも一歩、また一歩と後退しなくてはいけない。苦戦は必至で精神的なプレッシャーはすさまじかった。
ノックフォワード、スローフォワードなど軽微な反則のあとや、さまざまな場面でプレー再開の起点となるのがスクラムだ。
ラグビーの基本は「争奪と継続」と言われる。ボールの争奪戦に勝たなければ、攻撃する権利すら得られない。各チームはスクラムの強化に余念がないし、その最前列のプロップ(1番、3番)、フッカー(2番)の好選手を獲得、育成しようとする。
第一列両サイドのプロップは支柱という意味があり、スクラムの柱になる。中央のフッカーは押しの方向性などを調整する役目があり、ラインアウトのスローイングもあって器用な選手が多いが、プロップは大きくて力自慢の選手が並ぶ。
先日、コベルコ神戸スティーラーズのプロップだった山本幸輝さんのトークライブの進行役をする機会があった。
大阪・北浜のラグビー普及促進居酒屋「ラグビー部マーラー」は大入り満員。どのチームにいてもムードメーカーになる山本幸輝さんの明るいトークで笑顔が絶えなかった。
中学でラグビーを始めた頃からプロップ一筋。滋賀県の八幡工業高校から近畿大学、そしてヤマハ発動機ジュビロ(現・静岡ブルーレヴズ)に進んだ。
スクラムの奥深さを教えてくれたのは、ジュビロのスクラムコーチ長谷川慎さんだ。2019年のラグビーワールドカップ(RWC)で初のベスト8に進出した日本代表のスクラムを緻密な理論で作り上げた人である。
「スクラムで押されたとき、慎さんはFW第一列を責めません。後ろ5人の押しがどうだったか、そこをチェックします。フランカー(スクラムの両サイドにつく選手)は、次の展開に早く行きたいから顔をあげて見ていたりする。慎さんは、それはいいから、まずは押せと言うのです」
スクラムは8人で組むもの。後ろ5人の力を相手に伝えるのがプロップの役割というわけだ。
首の位置や相手とのバインド、姿勢など細かな技術があり、山本さんはその中で成長し、日本代表にも選ばれた。
しかし、2019年のRWCには出場できなかった。「あれが大きかったですね。ハンドリングのスキルとか、もっといろいろなスキルを学びたいと思いました」。
2021年度、器用な選手が多いコベルコ神戸スティーラーズ(神戸S)に移籍した。山本さんは自らを「旧式プロップ」と呼ぶ。
一昔前のプロップは、スクラムの強さが重要視され、運動量やハンドリングスキルは二の次だった。
しかし、最新のラグビーはプロップにもハンドリングスキル、相手の俊敏なバックスを止めるディフェンス能力を求める。その中で山本さんは精一杯の努力をしたが、神戸Sでの出場機会は少なかった。
この春、「やりきりました。今後はスクラムコーチを目指します」と現役引退を表明。神戸Sの普及アカデミーコーチとして再出発することになった。
もう一度ラグビー人生をやり直せるとしたら、どのポジションをやりたいか問いかけると、山本さんは「プロップ」と言った。「だって、こんなに面白いポジションありませんよ」。スクラムの最前列で体を張って来た男の誇りが垣間見えた。
いずれスクラムコーチになり、その奥深さを伝えていくのだろう。「旧式プロップ」。いい響きである。8人対8人が全力で押し合う姿はそれだけで胸を打たれるし、背筋がピンと伸びた姿勢で拮抗するスクラムは美しい。
現在のラグビーは、スピーディーな展開が重視され、スクラムを組む機会が減らされる傾向にあるが、少なくとも15人制のラグビーからスクラムが消えることはないだろう。
ボールの争奪こそが、ラグビーの原点だからだ。スクラムを全力で組み、パス、突進、タックル、そして、ラインアウトではジャンパーを持ち上げる。そのすべてを高いレベルでこなすプロップは尊敬に値する。
しかし、パスもキックも下手で、走るのも遅いけど、スクラムだけは負けないというプロップがチームを救うことがある。
それが、ラグビーの包容力だと信じたい。「旧式プロップ」が活躍できるラグビーの世界が、いつまでも続いてほしいと思うのだ。
![-みんなで治る病気に-喜連航平[九州KV]が「アルツハイマー啓発」と「おとなラグ..](https://rugby-rp.com/wp-content/uploads/2025/08/IMG_5832-272x153.jpg)