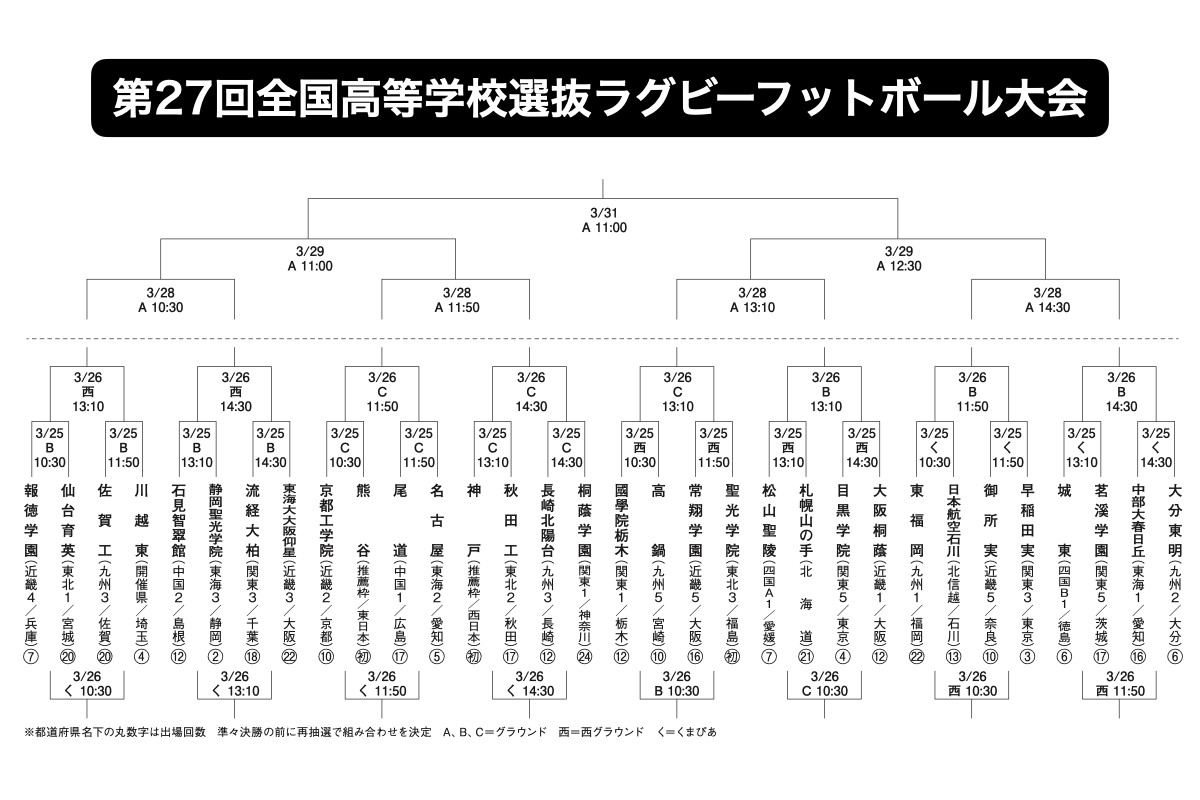【コラム】オールブラックスであり続ける。

2024年のサム・ケインに1987年のウェイン・シェルフォードを見た。先日、横浜・日産スタジアムでジャパンに10奪トライの64-19の大勝、オールブラックスの話である。
31歳。101キャップ獲得の7番、東京サントリーサンゴリアス所属のケインは、地味な仕事に汗をかく芝の上の労働者であり、肉弾バトルの現場を仕切る現場監督であり、グループの未来を見通す取締役のようだった。
感情を読ませぬ顔、かすかに哀しみをたたえる視線のまま、筋肉や骨を痛くさせるに違いない場所へ全身をねじこむ。いつもの姿といえば、そうなのだが、後半11分に代表デビューの21歳、ピーター・ラカイと交替するまで「ニュージーランド人が黒いジャージィを着て臨むテストマッチの基準」を後進に黙々と示した。なんだか、そのために生まれてきたみたいな感じすらした。
37年前。似た光景を見た。オールブラックスは第1回ワールドカップを無敵で制し(南アフリカは人種隔離政策への制裁で不参加)、約4ヶ月後に来日した。
東京・世田谷の三菱グループ施設での練習。アマチュア期のあのころは取材の規制はまるでない。駆け出し記者の身で連日通い、世界最高のチームのトレーニングや雰囲気を凝視できた。
客観的にはジャパンに負けるはずはない。なのにグラウンドはピリピリしていた。初戦の対日本選抜(ジャパンのひとつ下)の前日、代表デビューのSH、20歳のグレアム・バショップにひどい英語で「いまの気分は」と聞いた。
「とても緊張しています」
小さな声だった。「今回の遠征のメンバー入りはどのように知ったのですか」と質問したら「大工の仕事をしているときにラジオで」と言った。昔はそういうふうに発表された。優しい親方は「きょうは帰ってよし」と告げたらしい。クライストチャーチの建設現場の前の道を渡ったところのパブでひとりビールを何杯か飲んだ。
ほどなくバショップは楕円の王国の名手へと成長を遂げる。ジェイミー・ジョセフとともにプロの先駆として福岡のサニックスの一員となり、’99年のワールドカップでは胸に桜のジャージィをまとった。
あの’87年のツアー。ナンバー8のウェイン・シェルフォード主将はサム・ケインのごとく常に若手の手本であった。モールからちぎれて突破の練習。ボールを持つ選手が後方の仲間に手渡しする際の腕や膝の正しい位置をしつこくしつこく授ける。都心の宿舎の中庭のようなところで私服のままラインアウトを繰り返し、いちいち細部を整える場面にも遭遇した。
第3戦ではアジア・バーバリアンズを96-3で一蹴する。当時のジャパンの林敏之主将の著書にこんなくだりがある。「試合後、(オールブラックスの)プロップの選手に感想を聞くと」こう返した。
「全然ダメだ。きょうはミスが32回もあった」(『楕円球の詩』)
最終戦。ジャパンに106-4の圧勝。のちに日本代表監督となる14番、ジョン・カーワンが唯一の失トライをグラウンディングが不十分だと執拗に抗議した。
オールブラックスはオールブラックスであり続ける。そのときに強いだけではなく、先人の築いた「いついかなるときにおいても無敵であろうとする」態度、すなわち文化の継承を絶やさない。よって「若いチーム」というような言い訳のスペースはない。
先のジャパン戦もそうだった。前半22、25、31、34、40分の連続トライで白黒をつけて、後半は失速に映るが、むしろ愚直に体を張る防御に有史以来トップ級である凄みのようなものを覚えた。ブレイクダウンもタックルもスクラムも「力量差をいかして効率的にやろう」といったところがない。まっすぐなのだ。
ニュージーランドの頂点近辺のラグビー選手なら、だれだって11月3日のロンドンでの対イングランド、さらにはアイルランド、フランスとの連戦に選ばれたい。ジャパンを低く評価するわけでなく、ここは人情だろう。先遣メンバーはすでに離日しているので、中堅どころは焦燥や失意を抱く。新鋭には不安がつきまとう。そうした心の段差をサム・ケインのふるまいが埋めた。
1987年10月21日の午後。東京港区の芝パークホテル。国立競技場での日本選抜戦へ向かおうと黒のブレザー姿の集団が玄関を出ると、そこにいたカメラマンはシャッターを切れなかった。にらみつける緊迫がおそろしかったからだ。
時代は移り、プロ化は定着、いま「格下の国の正代表のひとつ下のチーム」を相手にそこまで張り詰めるとは想像しづらい。それでも日産スタジアムのサム・ケインの背中は黒き大河の先頭にある重みをたたえていた。本人が本年8月、代表主将でなくなったことについてコメントを残している。
「精神的な負担は軽くなった。同時にチームとその行く末が気になってしかたがない。それが自分の心の動きなんだ。そういうふうに何年もかけてプログラミングされてきたからね」(RNZ)
オールブラックスを生きるとはそういうことなのだ。
ニュージーランド・ヘラルド紙はジャパンを破った自国代表を「2軍」と書いた。なるほど問答無用の強さとは質が異なった。だから、かえって使命感が伝わってきた。

![将来は選手を「食」で支えたい。中村隼人[坂出第一/LO]](https://rugby-rp.com/wp-content/uploads/2024/10/IMG_7860-272x153.jpg)