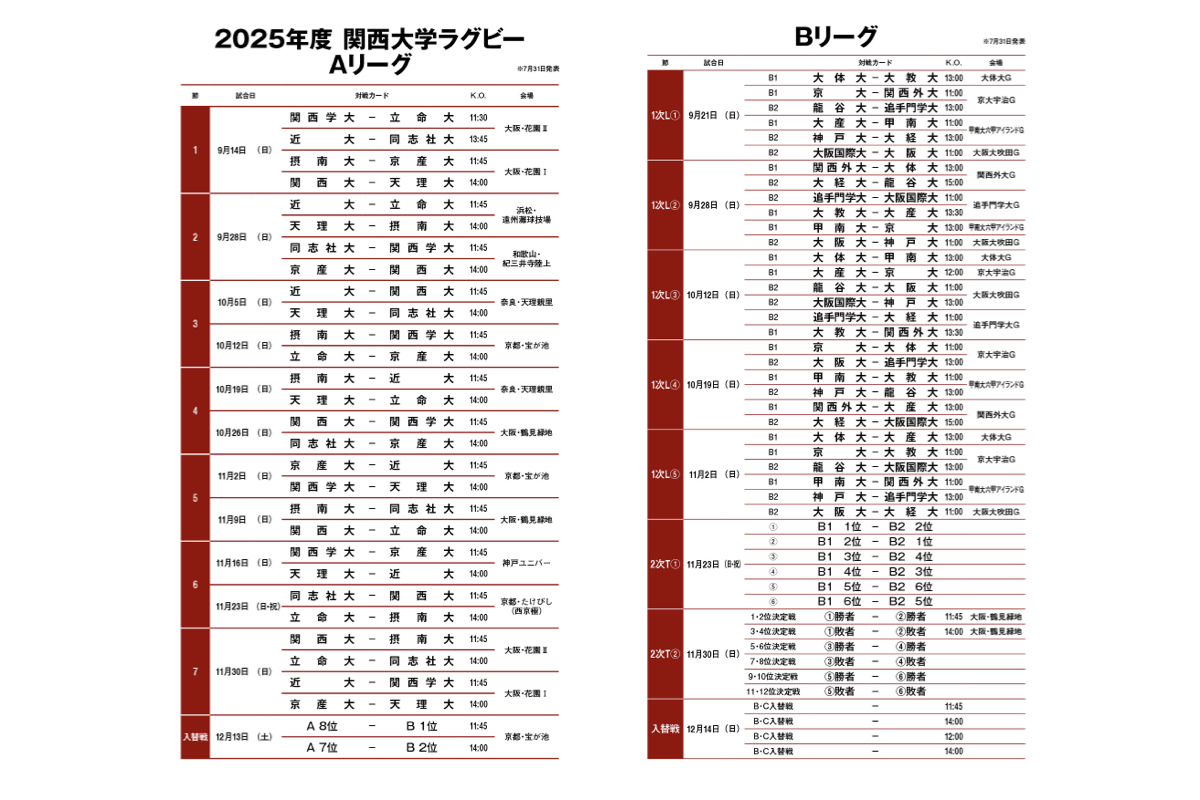【ラグリパWest】挑むということ。

高校ラグビーは3大公式戦のひとつ、春季大会の時期である。この大会は、年明けの新人戦(兼選抜大会予選)と秋の全国大会予選の間にはさまれている。
兵庫県の春季大会は「県民大会」という名で通っている。県内のトップを決めるこの大会は今年から「二部制」が導入された。
新人戦を参考に報徳学園や関西学院を含めた8チームのみが優勝を争う。県内で抜けた存在の2チームは4強戦から登場。残りは2つのリーグ戦にわかれ、2勝をすれば4強に上がる。
その下の二部は4つの合同を含め12チームで構成される。4つのグループに分かれ、リーグ戦をする。そこで2勝を挙げても、報徳学園や関西学院と戦う権利は与えられていない。一部の下位4チームと秋の全国大会予選のシードを決めるだけだ。
この二部制は大会を主導する兵庫県の全国高等学校体育連盟(略称:高体連)のラグビー専門部が、昨年から温めてきた腹案だ。隣の大阪府ではすでにこの形で、「府総体」と言われる春季大会は進められている。
このシステムを入れるひとつの側面として、春季大会はほかの2大会と比較して、県や府内での頂点を決めるため、全国大会には結びつかない、ということもある。また、トップチームとの実力差ということも大きい。
是認する声も多い。
「勝てなかったら、面白くない」
「力の合ったレベルでやるほうが身につく」
「時代に即した形」
そういったことが挙げられる。
一方で、最終的にその是非を問う「顧問会議」にこの腹案が下りて来た時、あるチームの顧問から声が上がったという。
「どんなチームでもチャンピオンシップに臨めないというのは、違和感が残る」
そんな意見も出たが、最終的には全会一致でこの二部制の導入に踏み切った。
この結果、兵庫県において、弱いチームが勝ち抜いて、最強のチームと試合できる可能性は秋の全国大会予選のみになった。新人戦はブロックが2つあるため、最強に挑戦できるかどうかは抽選の結果にゆだねられる。弱いチームの部員たちはその強さやふるまいに触れる機会もなくなる。
高校ラグビーの名門チームのひとつに佐賀工がある。冬の全国大会出場は42回連続52回。昨冬の103回大会も4強入りした。準優勝する東福岡に28-50。佐賀工の最高位は80回大会(2000年度)の準優勝である。
この佐賀工は佐賀の県予選において1試合を戦うのみだ。完勝が予想されるにもかかわらず、常にベストメンバーを起用する。
103回大会の県決勝は早稲田佐賀に106-0。チームは3人の高校日本代表全員を先発させた。SH井上達木(たつき)、SO服部亮太、CTB大和哲生(やまと・てっしょう)である。過去の県決勝では200点ゲームもあった。それでもこの姿勢はゆるがない。
以前、その理由を監督の枝吉巨樹(えだよし・おおき)が話してくれたことがある。
「先生の教えは、常に全力を出す、ということです。相手に1本たりとも触れさせない。スキを作らない。それでも相手が悔し涙を流しながら向かってくるなら、そこにリスペクトがあるんだ、という教えなのです」
先生とは小城博(おぎ・ひろし)。1946年(昭和21)創部の佐賀工ラグビーの中興の祖として、74歳の今でも総監督としてチームを支えている。
小城が大切にしているのは、相手チームの「挑む」という姿勢だ。点差ではない。
彼我の戦力を分析して、どこならスキがあるのか、どうすれば戦えるのか。それらを考える。そのアイデアを60分間実行する。もっとも大切なことは倒されても、倒されても、立ち上がり続ける。
その姿勢はただ単にひとつの試合のみならず、高校を出てからの人生につながってゆく。
社会に出て、どのような道を歩もうとも、勝ちっぱなしということは有り得ない。人生は小さいコンテストの連続である。たとえ敗者になることはあっても、高校時代に挑んだことを思い出し、またファイティングポーズをとる、とれる人になってほしいし、なるべきなのである。
その姿勢は授業や学校生活では得にくい。だからこその部活動であり、そこに肉体をぶつけ合いながら、みんなで痛みや苦しさを乗り越えてゆくラグビーが登場する。
作家の司馬遼太郎は「100戦100敗の人」という表現を使った。司馬はその負けっぱなしの人生を歩んだ人を愛したふしがある。100敗ではなく、100戦の方を見ていた。司馬も小城と同様、挑戦し続ける姿に力点を置いていたといえる。
優勝戦への門戸が開いている、ということは、挑めることの裏返しにほかならない。言い換えれば、人の成長に資する機会が多くなる、ということである。
同時に、ラグビーが一部の強豪チームによってのみ覇権が争われるなら、それは競技としての衰退にもつながってゆく。
思うように強化ができない、特に公立校顧問の先生方のご苦労は十分に理解できる。ただ、その中で挑む姿勢を取り続けることは、この国の将来につながってゆく。そういう気概を持って高校ラグビーに対峙していただければ、傍観者のひとりとして、幸せである。