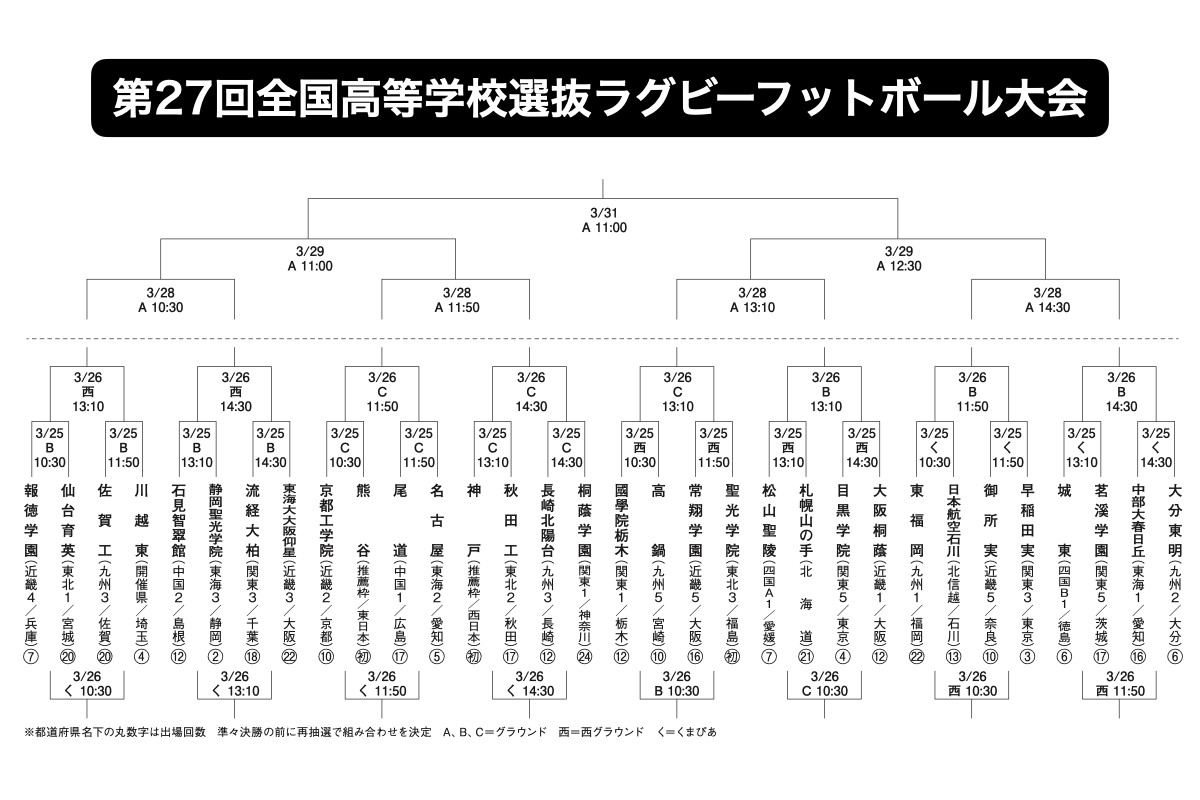【コラム】ロータックルが拓くラグビーの未来。

ラグビーが変わる。6月9日、日本ラグビーフットボール協会より「タックルの高さに関する試験的ガイドラインの導入」に関する通達が発信された。内容を要約すると、胸骨(胸郭前面の骨)の位置へのタックルはハイタックルとなり、複数でタックルする際も同様に胸骨より下でなければペナルティの対象となる。導入時期は本年9月1日からで、リーグワンを除くミニ、ジュニア、高校、大学、社会人、クラブの全カテゴリーで適用される。
※参考資料 試験的ガイドライン
https://rugby-japan.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/article/165341_6482cb7690e6a.pdf
トライによる得点が4点から5点に変わったのは、本稿筆者が高校2年の1992年だった。戦術的な選手の入替が可能になったのは1996年で、ビデオ映像によるプレー判定、いわゆるTMOが導入されたのが2001年だ。2008年の8月1日には、スクラム時のオフサイドラインが最後尾の選手の足から5メートル後方に下げられ、自陣22メートル線内へ持ち込んだボールを直接キックで外に出すとダイレクトタッチになるといった試験的実施ルール(ELVs)が正式に施行された。いずれもその後のラグビーの方向性を決める画期的なルール変更だったが、今回のガイドライン導入も、同等かそれ以上のインパクトがあると予想される。
通達の資料によれば、ボールキャリアーが胸部付近で保持しているボールに対し、防御側は「コンテスト」することは許されるものの、「タックル」すればペナルティが課される。このあたりの線引きは非常に微妙だが、ハイスピードかつ高い強度で相手の胸にヒットするプレーは、ほぼPK(場合によってはカード)になると考えていいだろう。現在主流の1人目が下に入り、2人目が上体に当たってボールを殺しにいくダブルタックルも、そのままなら反則とされる可能性が高い。
オフロードパスが全盛の現代ラグビーにおいて、胸に抱えたボールへの防御側のアプローチが難しくなるのだから、プレーに多大な影響が及ぶのは必至だ。タックラーはより正確なタックルスキルと状況判断力を身につけなければならないし、チームとしてもこれまで以上に緻密な防御システムの構築が求められる。反対にアタックでは、上半身の自由度が増すアドバンテージを活かした新しい攻撃法が考案されるだろう。
「胸部へのタックル禁止」の最大の狙いは、近年国際ラグビー界で深刻な問題となっている頭部外傷の対策だ。ワールドラグビーが発表したデータによれば、タックルの際にタックラーの頭部がボールキャリアーの胸骨より上にある場合、脳震盪のリスクが4.2倍高まるという。またフランスのローカルレベルで今回のガイドラインを試験的に実施したところ、頭と頭が衝突する事例が64パーセント、脳震盪は23パーセント減少したという結果も出ている。
胸へのタックルまで反則をとられてはラグビーにならない、と感じる人もおられるかもしれない。しかし脳震盪の問題は、もはやラグビー競技の存続にも関わるほどの差し迫った状況にある。
2020年12月、元イングランド代表HOで2003年のワールドカップ優勝メンバーでもあるスティーヴ・トンプソンら8人の元選手が、脳の損傷により早期発症型の認知症になったのは競技団体が適切な対策を講じなかったためとして、国際統括機関であるワールドラグビーなどを相手に訴訟を検討していることが報じられた。トンプソンは2003年ワールドカップについて「大会に出たことすら思い出せない」と話しており、他にも元ウエールズ代表キャプテンのFL/NO8ライアン・ジョーンズや、当時世界最高のタイトヘッドPRと称された元ニュージーランド代表のカール・ハイマンも、早期発症型認知症と診断されたことを明かしている。
日本の国内シーンを見ても、抜本的な改革が不可欠であることに疑念の余地はない。トップレベルのプロ選手がひしめくリーグワンのゲームでは、ヒヤリとするシーンを頻繁に目にする。2022-23シーズンのディビジョン1の公式記録を調べたところ、リーグ戦全96試合でHIA(Head Injury Assessment/脳震盪評価法)のチェックが入ったケースは59件あり、うち41件はそのまま交替している。2試合に1件の割合で脳震盪と疑われる事例が発生している計算であり、空恐ろしさすら感じる数字だ。なぜか試合から遠ざかっている主軸選手の様子をチーム関係者に尋ねた際、「実は脳震盪で…」と内実を知らされることも少なくない。
今回の試験的導入でリーグワンは対象外となったが、これはワールドカップイヤーによる現場レベルの混乱を避けるためだろう。ワールドカップでこれまで同様の基準で戦った選手たちが、帰国後の国内リーグでいきなり胸より下のタックルに対応しなければならないというのは酷すぎる。2024年以降はそうした最高峰カテゴリー、おそらくテストマッチでも、本ルールが導入される可能性は高いと予想する。
断っておくが、むやみに不安を煽りたいわけではない。ラグビーの未来のために、関係するすべての人々が、ガイドライン導入の背景を理解し、覚悟を持って、安全な競技の実現に取り組んでいくべきというのが本稿の主意だ。激しいコリジョンをともなう(そこに魅力がある)スポーツだけに、頭部外傷をゼロにするのは困難かもしれない。それでも、極限までゼロを追求する努力を怠ってはならない。これだけのことをやっているといい切れる体制を整えてこそ、将来を担う子どもたちにも自信を持ってラグビーを勧められると考える。
そして新たなルールの導入は、まったく新しい戦法やプレーが生まれるチャンスでもある。事実、高校や大学の中には、5月にワールドラグビーの評議委員会で試験的ガイドラインの推奨が承認されたことを受け、日本での採用を見越して早い段階から準備してきたチームがいくつもある。なんと頼もしいことか。
そもそも低く食い込んで相手を倒し切るロータックルは、日本ラグビーにとって永遠の生命線だ。光速の出足と無尽蔵のフィットネスでスペースと時間を奪い、オフロードでつなごうとする相手アタックを寸断し続ける。そんな世界を驚かせる革新的な防御法が生み出されることを期待しよう。