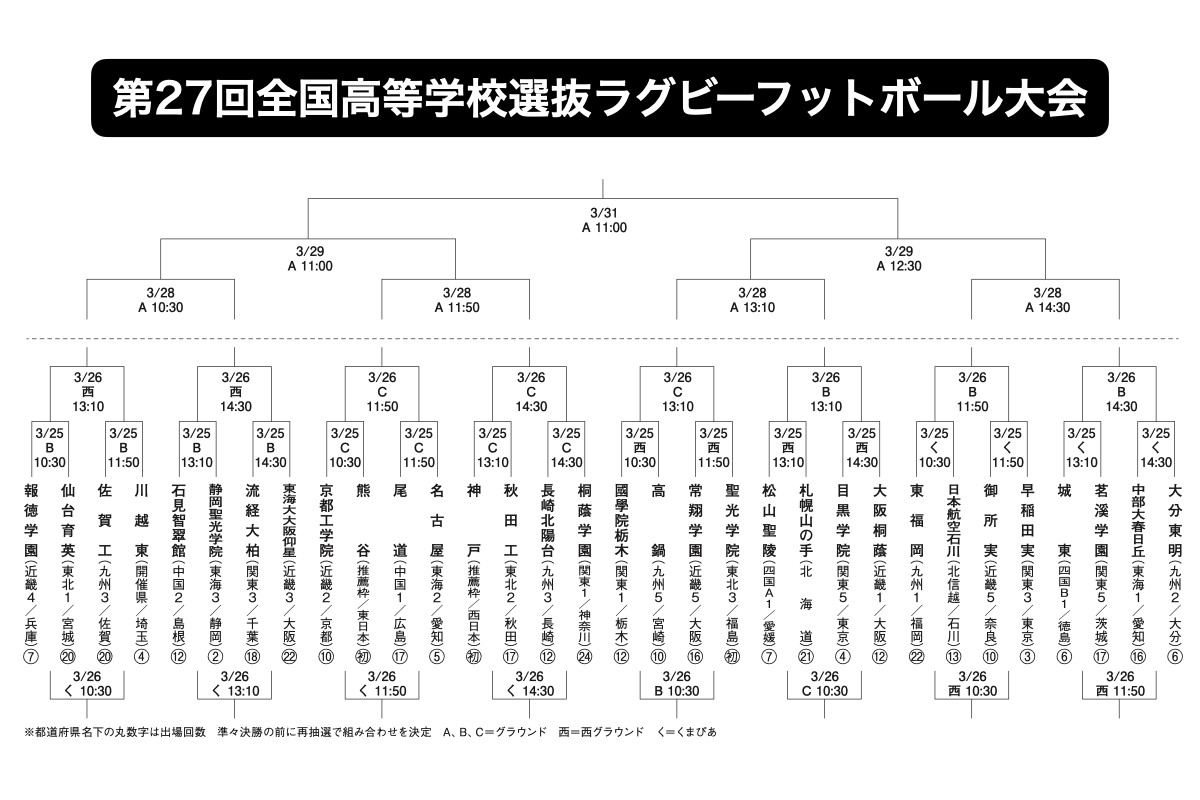【コラム】自分たちだけの世界。

ゴールポストの裏の裏。薄暗いスペースに「世界」を見た。
スクラムドクター、長谷川慎さん(ハイパフォーマンスコーチ)の声が響き渡る。
語りかける。
叱咤する。
問いかけ、褒め、キーワードを何度も言う。
ある秋の日の17時半過ぎ。日はとっぷりと暮れていた。薄明かりの中、いいものを見た。
静岡県磐田市、ヤマハ発動機ジュビロ大久保グラウンドにあるクラブハウス側の逆サイド。
インゴールの後方にある土手と生け垣を越えたところの窪みに男たちが密集していた。
2016年にできたスクラム練習場がそこにある。平地部分と傾斜のついたスペースがあり、会社の技術者たちが知恵を結集して作ってくれた特別なスクラムマシーンも設置されている。
以前は駐車場だった場所だ。
ジュビロには、長い時間をかけてスクラムを強化してきた歴史がある。
その意志と積み上げてきた時間、手に入れた武器は、チームカルチャーとして浸透し、特にFWの選手たちにとっては、プライドを懸けるものとなっている。フロントローだけではなく、LOもバックローも、毎回のスクラムで押すことに集中する。
スクラム練習の約30分は、異空間だった。薄暗いスペースに立った瞬間、全員、スイッチが入った。
体をぶつけ合う直前の静寂。
組み合ったときの衝撃音。
長谷川コーチの声が響く。
「足を詰めろ!」
ザッ、ザッ、ザッ。人工芝に食い込んだスパイクが小刻みに動く。
ブレイク後の深い吐息。選手たちが話し、互いに気づいたことを言い合う。そして、また組む。
セッションの途中、コーチの指示を聞くため、円陣を組む時間があった。輪が解けて、あらためて8人と8人が向き合う。そのとき、セットが遅れた。
「ヤマハのスクラムは、相手より遅くセットするのか」
長谷川コーチはそう言うと、「坂をのぼりながら話し合え」と選手たちに指示を出した。
大男たちが会話しながら歩き出した。
その数秒後だった。同コーチは、「セーット」と大きく叫んだ。
全員が素早くもとの位置に戻る。今度はすぐに肩を寄せ合い、沈んだ。鋭くヒット。全力で押し合う。
「この感覚を忘れるな」
ひとつの言葉で空気が変わる。魔法の声のようだった。
スクラム練習の最後の円陣、入団8年目の伊藤平一郎が全員に言った。
「きついときにも自分たちのやるべきことをやり、強いスクラムを組めるやつがファーストジャージーを着ることができるんだ」
伊藤は早大時代はHO。ヤマハに入って長谷川コーチに右PR転向を勧められた。
1番の経験はあった。しかし、「3番は大きな人がやるもの」と思っていた。175センチしかない自分がやれるのか半信半疑だった。しかし、コーチを信じて練習し続けたら2年で日本代表に選ばれた。
魔法にかけられたような感じでしたか?
伊藤は、長谷川コーチのことを「ひと言で変えられる人」と話す。でも、それは魔法ではないと言った。
「ひと言で、プレーも、空気もメンタルも変えられる。そのとき必要なことを言ってくれる。的確なんです。そして、できないことは言わない」
ちょっとしたことを変えると、結果が大きく変わる。そこに気づかせてくれる。
大事なことは何度でも言って、やらせて、体と頭に染み込ませる。
「井野川(基知)コーチのウエートトレーニングも加わって、腕が上がらず、シャンプーができないくらいになったこともあります」
強力なパックを作り上げる過程は職人技だ。
どこからか持ってきた言葉や理論、練習法ではない。すべて自身で作り上げたものだ。
だから選手たちもプライドを持つ。そこで負けるのは、自分たちを否定されたことになるからだ。
伊藤は、「スクラムにかける熱量ではどこのチームにも負けない」と言った。
「慎さんが言うだけでも、ベテランが伝えるだけでもなく、若手もどん欲に知りたいことを聞いてくる」
こうしてほしい。そうした方がいい。年齢に関係なく、気づいたことを指摘し合う。試合と変わらぬ集中力で一本一本、全力で組む。
日本代表のスクラムを世界規格に進化させ、サクラのジャージーがワールドカップで8強に進出する土台を作った人は以前言っていた。
2011年にヤマハのコーチに就任する前、単身でフランスに渡った時に感じたものは、指導者としての原点になった。
「フランスに行ってわかったことがありました。あちらに行けばフランスのスクラム、というものを学べると思っていた。でも、そんなものはどこにもなかった。ただ、それぞれのクラブに、スクラムに情熱を燃やしているコーチがいて、彼らが独自に考えたものが、それぞれのクラブで生きていた。つまり自分で、オリジナリティーのあるものを考える。そして、信念を持ってそれを伝えることが大事。そう気づきました」
静岡県西部の静かな街。そこにある広いグラウンドの隅っこから、世界に出ていく選手たちが育つ。
夢のあるストーリーは長谷川コーチが紡ぎ始めたのだけど、本人は常に「主役は選手」と言う。
その日も、「みんな、頑張るでしょ。いい練習しているでしょう」と細い目をさらに細くして言った。
元世界王者、八重樫東さんを迎えてのボクシングトレーニング実施の取材で、10月最終週の月曜から2日間、磐田を訪れた。
「スクラムは、火曜の夕方にやりますよ」
グラウンド到着後にその言葉を聞いて、2日目の午前練が終わったら帰る予定を変更した。
スクラムドクターの言葉の裏に、「俺たちの世界を見なきゃ損だよ」のメッセージが隠れているような気がしたからだ。
正解だった。
【筆者プロフィール】
田村一博(たむら・かずひろ)
1964年10月21日生まれ。1989年4月、株式会社ベースボール・マガジン社入社。ラグビーマガジン編集部勤務=4年、週刊ベースボール編集部勤務=4年を経て、1997年からラグビーマガジン編集長。