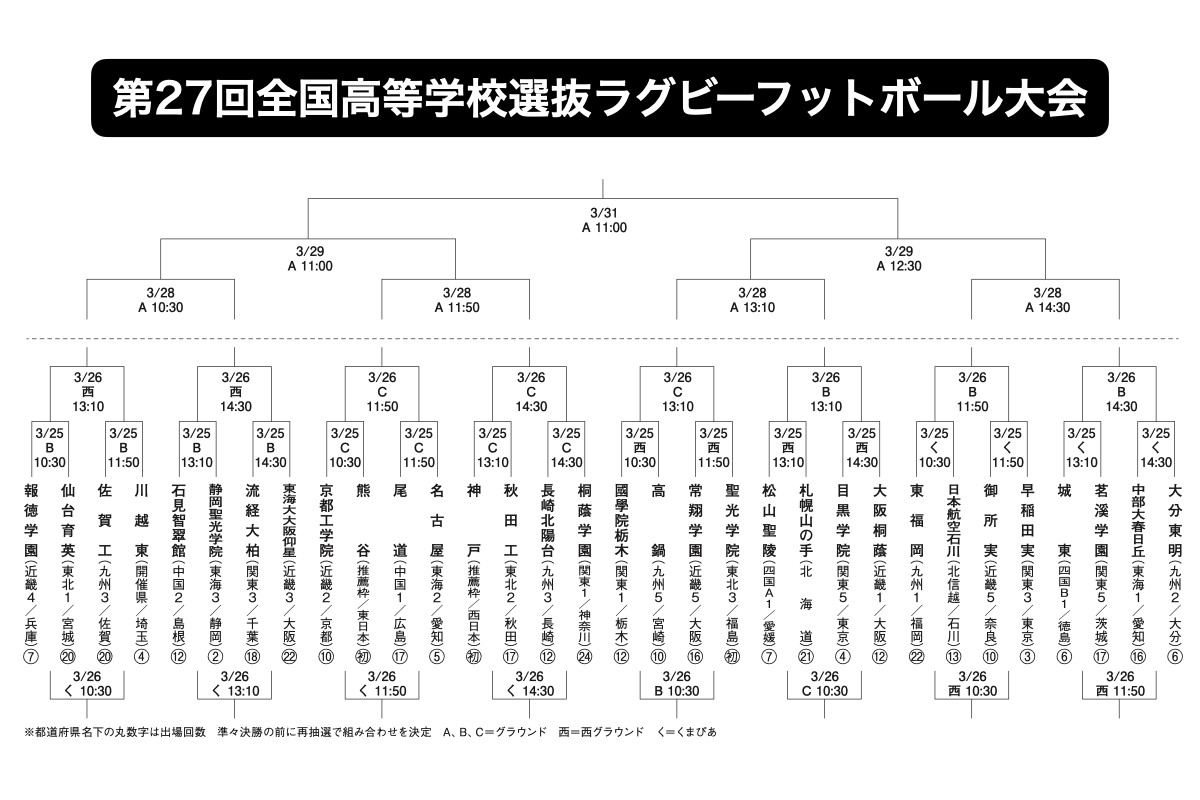【コラム】みんなの菅平。

蹴り上げられた茶色の革ボールが、真っ青な青空に吸い込まれていく。ラグビーを始めた頃、その瞬間が好きだった。
菅平で見る空は、都内より近くにある感じがした。
夏合宿の午前練。深い霧の日は、少しだけ得した気分になった。
辛いランパス中も、口をパクパクすれば水分を摂取できそうで。ヘロヘロな姿を、怖い先輩から隠せるようにも思った。
大学時代は、もう30年以上前のこと。でも、記憶の中の空は真っ青なままだ。朝モヤは白い。グラウンドは土色だけどね。
卒業後も、OB戦やクラブの試合、取材などで、何度も、何年も訪れた場所。
その菅平が、今年はいつもより静かだ。
昨年8月はラグビーだけで820チーム(高校455、大学192、社会人11、小中他162)が彼の地を訪れた。サッカーの217チームを合わせると、2競技だけで1000を超えるチームが高原の芝を駆けていたのに。
今年、菅平を訪れるラグビーチームは30前後のようだ。
彼の地でラグビーマンたちの訪れを待っている宿の方々は、寂しくて、不安だろう。胸中を思うと、こちらも辛くなる。
幸い、菅平の住人の方々の表情は、『WE ARE スガダイラーズ・プロジェクト』を通して、SNS越しに見ることができる。
いろんな宿の方が登場し、こちらに呼びかける。
見覚えのある玄関。懐かしい人の顔。「来年こそは、いつもの菅平で、いつもの皆さんをお待ちしております。スリーチアーズフォースガダイラーズ ヒプ、ヒプ ヒプ」の声に、こちらも笑顔になる。
あ、大学の後輩たちが、それに対してエールの動画を流している。
いいぞ。
3月、春休みに小学生、中学生の団体を受け入れるはずだったのに、全部なくなった。
4月からゴールデンウィーク、7月にかけて、社員研修や林間学校、ラグビーやサッカーの大会もすべてキャンセル。菅平高原は、コロナ禍により大きなダメージを受けた。
そんな危機的状況の中で、ただ黙って耐えているだけでは飲み込まれてしまう。立ち上がらないと。
そんなスピリットで動き出したのが『WE ARE スガダイラーズ・プロジェクト』。クラウドファンディングで寄付を募り、それを菅平高原旅館組合の運営費に充てる予定だ。
7月20日から始まり、多くの人たちが賛同している。
先月、旅館組合の副会長を務める大久保寿幸さんと話す機会があった。このプロジェクトが動き出してすぐ、自身が経営する宿に宿泊していたチームの部員たちがSNS上に想い出の動画などを「#WE ARE スガダイラーズ」の文字とともにアップしていることを知り、ほっこりした。
その輪はどんどん広がった。応援してくれる人たちがたくさんいると知った。
大久保さんは、同プロジェクトのリーダーを務める。でも、そのポジションに立つと覚悟を決めるまでは葛藤があった。
助けてください。寄付してください。当事者が、そんな声を挙げていいものかと悩んだ。
それは自分だけの感情ではなかった。周囲には、頭を下げるのは恥ずかしいと思う人たちもいた。面倒なことは御免だよ。そういう人も。
終わりの見えないトンネルの中で、落ち込んでいる人の存在も知っていた大久保さん。「(宿の経営を)やめるタイミングを探している」と口にする人と会っても、無責任な励ましを口にはできなかった。
そんな状況から、リーダーとして動き回る心境になれたのは、プロジェクトの準備期間に触れ合った人たちや、SNS経由で届く人たちの思いを知り、「菅平は住人たちだけのものではない」と感じたからだ。
「寄付でお金を集めることに、私自身、最初は気持ちの切り替えができませんでした。菅平(の人たち自身が)が『助けて』と言わない形でやりたいと思ったこともあります。でも、あらためて、菅平は多くの人たちの想い出が詰まっている大切な場所と分かった。だから、僕らが合宿の聖地の住人として、プライドを持ってここを守っていきます。だから力を貸してよ、と。そう考えられるようになったんです」
大久保さんが覚悟を決めると、賛同してくれる人たちが増えた。その同じ意志を持った仲間たちが、高原の住人たちに説明して回ったり、動画撮影の協力を依頼するうちに、町全体がひとつになっていった。
その輪は旅館組合の枠も超え、お土産物店や電気店などが属する商工組合にも広がる。
プロジェクトリーダーはいま、「どうやって、もっと目立とうか。この渦をさらに大きくしていくにはどうしたらいいか、と考えています」と言う。「隠れていないで、前へ、前へ、です」と笑った。
私自身、都内でバスに乗っていても、降りる時、自然と「ありがとうございます」と声が出る。
大学時代、泊まっていた菅平国際ロッジ(現ベルニナ)のバスで遠いグラウンドに連れていってもらった。その時の降車時のクセが35年近く経っても抜けない。
当時はまだ、長野新幹線はなかった。先輩に、横川駅では釜飯を買うのだと習い、その容器がしばらくアパートにあった。
新品の靴を夏合宿に履いていったら、入れ替わりで山を降りるチームの誰かが履いて帰ったのだろう、練習用のボロボロのアップシューズで東京に戻ることになった年もある。
実は夏合宿が楽しみだった。
そう言えば、練習がラクだったのだろうと言われそうだが、特に下級生の頃は、アパートでの毎日の食事にも苦労していたから、きつい練習さえ乗り切れば、おいしいご飯が出てくる日々が嬉しかった。
当時は、コーラなどの1・5リットルの空き瓶を酒屋などに持っていけば30円だったかな、それくらい貰えたので、それでハムカツなどを買い、食事にしていたときもあった。
菅平では、そんなことをしなくても美味しいご飯がいくらでも食べられた。
朝6時ぐらいには起きて、早朝から9時頃までランパスなど、きつい練習をやって、朝ごはん。
食べ終えたら、午後練に向けて、また寝る。昼ごはんのパンやバナナを食べ、また少し寝て、グラウンドへ。試合と練習を連日繰り返し、クタクタになった。
1年生時は抵抗力が弱くなり、バイ菌が入って頬が腫れ、先輩に上田の病院まで連れていってもらった。太もものすり傷もジュクジュクに膿んだ。
3年生の時だったかな。半日オフの日、女子マネが留守のあいだに部屋に忍び込むことになった。真面目な先輩が見張り役になった姿を見て、なんともいえない気持ちになったなあ。
菅平の夏の記憶は、どうして色が濃いのだろう。
【筆者プロフィール】
田村一博(たむら・かずひろ)
1964年10月21日生まれ。1989年4月、株式会社ベースボール・マガジン社入社。ラグビーマガジン編集部勤務=4年、週刊ベースボール編集部勤務=4年を経て、1997年からラグビーマガジン編集長。

![【ラグリパWest】マイコ、再び。飯泉苺子 [東京・荏原第六中学校2年生]](https://rugby-rp.com/wp-content/uploads/2020/08/iiizumi_IMG_4891.jpeg)