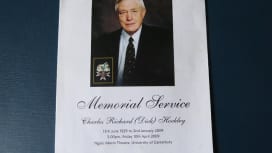【中川文如コラム】 早慶2番勝負

今泉清が独走トライを挙げた早明戦があったからこそ、選手権優勝を決めた吉田義人のトライはより熱を帯びた。超軽量FWの早大が圧倒的不利の下馬評を覆した1981年度の早明戦も、最後、選手権の再戦で明大のパワーに屈する結末が待っていた。
時代は違うけれど、全国大学選手権準々決勝の早慶戦を見ていて、ふと、そんな一連の場面が頭をよぎった。
この競技本来の対抗戦文化とナンバー1決定にこだわるトーナメントの折衷。すなわち高いレベルで力が拮抗すれば、年に2度の真剣勝負が実現する。日本の大学ラグビーならではの舞台設定、1試合限定では味わえないストーリーが紡がれる。今回は早慶2番勝負。
伏線は11月23日の対抗戦に敷かれていた。圧倒的に主導権を握ったのは慶大で、敗れたのも慶大だった。密集の近場勝負にこだわりすぎたのが敗因。「そのエリアで早大防御が人数をかけてきて、うちのリズムにならなかった」。主将のSO古田京の敗戦の弁だった。
あれから1か月。慶大の修正力は際立った。近場勝負から逃げない。でも、こだわらない。ピッチの幅と奥行きを広く使った。
キックオフ直後から大きく展開。最初のトライは古田のキックがもたらした。早大のエリアマネジャー、最後尾に構えたSO岸岡智樹のさらに背後に蹴り込み、バウンド2回で処理させた時点で勝負あり。1か月前のコントロール重視ではない、遠くへ振り抜く意志が左足に宿っていた。味方のチャージ、インゴールへ。
後半24分、敵陣ゴール前のスクラムから古田のトライは導かれた。押し込んでも、こだわらない。NO8山中侃、SH江嵜真悟と経由されたパスが古田に渡った。対抗戦の背景があるから、単純なようで思慮深い選択なのだ。早大防御に的を絞らせなかった。
このトライとゴールで19-15。試合のハイライトになる、はずだった。
残り30秒のマイボールスクラムで取られた反則。最後のプレーで早大WTB佐々木尚に奪われた逆転トライ。レフェリングのあや。控えだった4年生のプライドにかけて先発起用した敵将・相良南海夫監督の勝負勘。
「力の差があるとは思わない。ただ、勝負事にはさまざまな要素があるんだな、と」。確かにさまざまな要素が交錯した。準備を尽くした古田、2度目の敗戦の弁に感情移入したくなる。でも、2度競って、2度負けた。やっぱり力の差はあったのだと感じる。
将来の日本代表を担いそうな原石をBKにそろえる早大の個の能力の総和。長年の低迷を経てなお「うれしいのではなく、ほっとした」と主将のFL佐藤真吾に言わせたのは、創部100周年の歴史に宿る勝者のメンタリティーにほかならない。そういう差が、2番勝負の160分間から伝わってきた。
準決勝は、2度目の早明戦になる。
攻撃の引き出しを多く持つ明大の決断が、勝負の鍵になるだろう。12月2日の対戦を振り返れば、そこがあやふやなうち、早大に突き放されていた。局地戦か、展開か。まず立脚点を定めたい。定めてこそ、その裏、つまり引き出しが生きる。
早大は、準々決勝に続いて受けて立つ役回りを強いられる。だから、課題のスクラムとラインアウトで細部に目を凝らしたい。精度を問う前に、セットプレーのセットの遅さが気になる。まずは気構え、心構えの問題だ。せっかくの、日本で最もアップビートなSHの齋藤直人が、これでは生かされない。
一点突破の個性を組織の中で輝かせるのが早大の伝統だとするならば、15人でもっと試合のテンポを早め、もっと齋藤を輝かせた方がいい。いまの齋藤は孤軍奮闘の域を出ていないと思う。