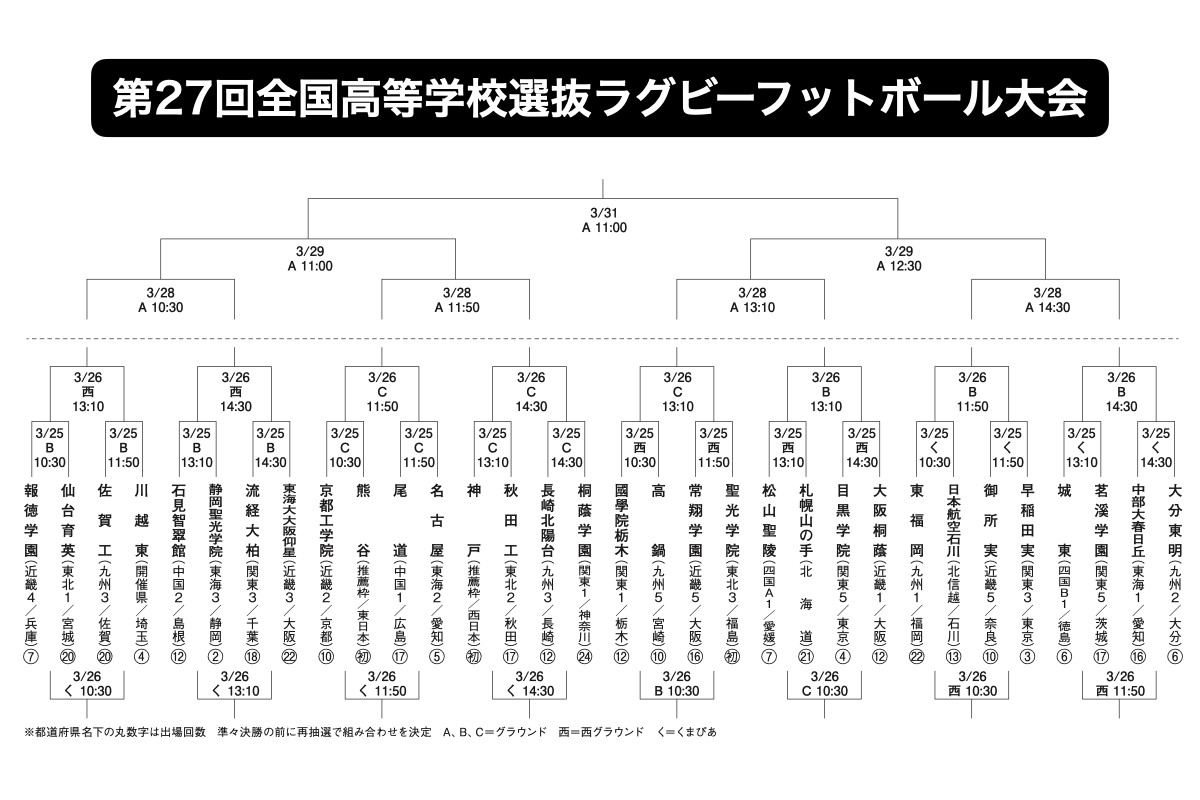ギョウザ耳列伝 vol.15 篠塚公史

篠塚公史
<埼玉工大深谷高(現・正智深谷高)―法大―サントリー>
男は黙って…。
かつて三船敏郎がそう言うテレビCMがあった。「男は黙って○○○○ビール」と。いつも試合で、いぶし銀の光を放つ篠塚公史(こうじ)なら、こう言うのだろう。
「男は黙ってサントリービール」
玄人ファンは篠塚の偉大さを知っている。ラインアウトのジャンプは一級品。時には相手ボールも鋭く奪取する。ブレイクダウンでは地味にからだを張る。ボールを持って派手にゲインすることは少ないけれど、篠塚がいなければ、おそらくサントリーの連続攻撃も威力半減となるのではないか。
2月15日。日本選手権2回戦の神戸製鋼戦もそうだった。ひたむきなプレーでサントリーの勝利に貢献した。試合後の秩父宮ラグビー場の薄暗い通路。「ナイスプレー」と声をかければ、シャワーを浴びたシノは196センチのからだをひょいと傾け、少しはにかんだ。
「目立たないプレーが好きなんで…」
いいなあ、この雰囲気。ラグビーというスポーツにはトライゲッターやボールキャリアーも大事だが、コンタクトエリアで黙々と仕事するこの類の「働き者」も必要なのだ。
「目立つプレーはみんなにやってもらって、僕はサポートプレーに専念しているんです。もう片方の(ロックの)真壁(伸弥)がボールキャリアーでガンガンいってくれるので、その後のカバーをしようかなって。みんながボールキャリアーばかりになると、ブレイクダウンでボールが出ないでしょ。ははは」
サントリーは不思議なチームだ。し烈なポジション争いをしていながら、ここぞという時にはチームに一体感とリズムが生まれる。ギアが一段階、上がるのである。
「もう負けたら最後なので、チームが一丸となって戦おうという気持ちが今まで以上にあったのかなと思います。コーチたちに言われる前に自分たちでやろうと。まあチームビルトの一環として、飲み会もありました」
飲み会はもちろん、サントリービールである。ほどよく笑いが出たところで、『ギョウザ耳』の話題を振る。さりげなく。よかった。ちゃんとこの奇跡の連載を読んでもらっていた。なら、話ははやい。
でも、前回はサントリーの後輩の真壁伸弥だった。後輩の後に登場願うのはどうなのか。イヤではないか。「真壁さんの後です。大丈夫でしょうか?」と聞いてみた。
「もちろん。真壁キャプテンのあとに登場できて光栄です。はっはっは」
不気味な笑いである。コワくなって、「ほんとにほんとう?」と念を押した。
「真壁、耳が沸いていたのかって、びっくりしました。知らなかった。あいつも苦労しているんですね」
つぶれたギョウザ耳は『我慢』の象徴だった。篠塚の右耳が形を変えたのは、9年前、サントリー入社1年目の夏合宿だった。
あの北海道・網走合宿のスクラム練習である。当時の監督がスクラムを大事にする清宮克幸氏(現ヤマハ監督)、スクラムコーチが「ドクター・スクラム」の異名をとる長谷川慎コーチだった。どうしたってスクラム練習は苛烈を極める。
「清宮さんやシンさんたちが、スクラムにこだわっていたので。1年目なので、痛いとは言えず…。必死だったんです。試合に出たかったから。我慢してやり続けました」
その夏合宿では左ロックの4番の位置に入っていた。2番のフッカーが青木佑輔だった。
「もう、何だろう。スクラムで青木の腰骨がずっと右耳に当たって…。スクラムを組みながら、ずるずると前に出る練習だったんですけど、ずっと(青木の)腰骨が耳にこすれていて…。ずるっずるって」
ああ。痛そうだ。なんだか、こちらの右耳も痛くなってきた。
「で、スクラムブレイクしたら、耳が熱くなっていたのです」
それがギョウザ耳の端緒だった。その熱さが痛みに変わっていく。激痛に。
「やったときは熱かったんですけど、痛かったのは、その後ですね。寝るにしろ、もうジンジンして、寝返りも打てないんですから。起きている時も、風が耳に触れるだけで痛くて痛くて。網走の涼しい風が熱くて熱くて…」
耳にたまった血は即、抜いた。スクラム組んでまた、たまって、また抜いて。
「で、何回か、3、4回繰り返しているうちに、“もういいや”って放置しました。アイシングして、固めちゃおうって。シーズン中もずっと、痛かった」
かわいそうに腫れた右耳にはリング(輪)をあてて黒色のヘッドキャップをつけて、試合に出場した。1年目は6番のフランカーだった。黒いヘッドのハードタックラー。
「ヘッドキャップをかぶるのがイヤだったんですけど。大学の時はしていませんでした」
なぜ。カッコ悪いから?
「それが一番です。若い時はやっぱり、そこじゃないですか」
これが社会人の洗礼だったのだろう。耳の痛みが、世の中の厳しさを教えたのだった。何事も苦労を苦労と思わず、痛みにも泣き事を言わず、黙って生きるのだ、と。
忍耐を学びましたか?
「そうですね。高校の時から、“耐えて勝つ”とずっと言われていました。耐えて、耐えて、耐えれば、勝てるって。耐えることが、勝つ原動力になるって。ラグビーって、基本的には我慢強さでしょ。我慢、我慢、我慢が一番、重要かなって思います。ディフェンスの時はオフサイドしてはいけないし、ブレイクダウンで頭にきても手を出してはいけない。アタックに関してもチームのルールがあって、全てに関して我慢が必要なんです」
いい話である。高校の教科書に載せてほしいコメントである。篠塚は社会人になって、ホンモノの我慢を覚えたのだろう。
「大学までは好き勝手していたので。そう言われると、そうですね」
では、左耳のギョウザ耳はいつ?
「左耳に関してはまったく覚えてないんです。今シーズンの最初の方かな。気がついたら、血が固まっていました。左耳は、右耳で勉強していたから、ちょっと腫れだしたら、クリップみたいなものをはさんで。だから、それほど膨れてないでしょ」
腫れたら、まずいですか?
「見た目がこわいじゃないですか」
でもギョウザ耳にはいいこともある。ギョウザ耳同士の絆が深まる。話題のタネになることもある。篠塚は赤坂でスーパー本部の営業を担当している。
「最初、新しく担当を持ったところにあいさつにいくと、身長もそうなんですけど、耳がつぶれているから、柔道かラグビーをやっているのかという話になるんです。自分は会話がそれほど得意なほうじゃないので、向こうから話題を振ってもらえるのはありがたい。そこからいい具合に話が進むことがある。営業に役立っています」
ひと呼吸、間を置き、破顔一笑。
「そう、“営業耳”です。僕のギョウザ耳は営業耳です」
ところで、篠塚は9年目の今シーズン、「トップリーグ100試合」を達成した。昨年10月11日の近鉄戦である。ちなみに初試合は、2006年9月3日の神戸製鋼戦だった。
「個人的にはトップリーグのキャップ数とか気にしたことなかったので…。100試合出ても、チームに貢献しなかったら意味がない。数じゃない。やっぱり、試合での存在感が大事です。目立たないプレーをするんですけど、存在感って大事なんです」
コトバに自負がにじむ。しぶいねえ。そう言われると、かすかな喜びを感じるそうだ。トライをするのではなく、トライに至るプロセスのプレーに参加する。献身である。
「トライのきっかけになるプレーに参加できればいいんです」
朗報である。3月上旬には3人目の子どもが誕生する予定である。長男、次男に続く、3人目。「おそらく男みたいです」
子どもたちには、ラグビーを無理にさせるつもりはない。ただ、耳についてはひとコト、父親として言いたいことがある。
大事にしろっていうことですか、と言うと、いぶし銀の31歳はニカッと笑った。
「でも、つぶれたほうがカッコいい」
2015年2月20日掲載
※ 『ギョウザ耳列伝』は隔週金曜日更新
【筆者プロフィール】
松瀬 学(まつせ まなぶ)
ノンフィクションライター。1960年生まれ。福岡県立修猷館高校、早稲田大学のラグビー部で活躍。早大卒業後、共同通信社に入社。運動部記者として、プロ野球、大相撲、オリンピックなどの取材を担当。96年から4年間はニューヨーク支局に勤務。2002年に同社退社後、ノンフィクションライターに転身。人物モノ、五輪モノを得意とする。『汚れた金メダル 中国ドーピング疑惑を追う』(文藝春秋)でミズノスポーツライター賞受賞。著書に『日本を想い、イラクを翔けた ラガー外交官・奥克彦の生涯 』(新潮社)、『ラグビーガールズ 楕円球に恋して』(小学館)、『負げねっすよ、釜石 鉄と魚とラグビーの街の復興ドキュメント』(光文社)、『なぜ東京五輪招致は成功したのか?』(扶桑社新書)など多数。