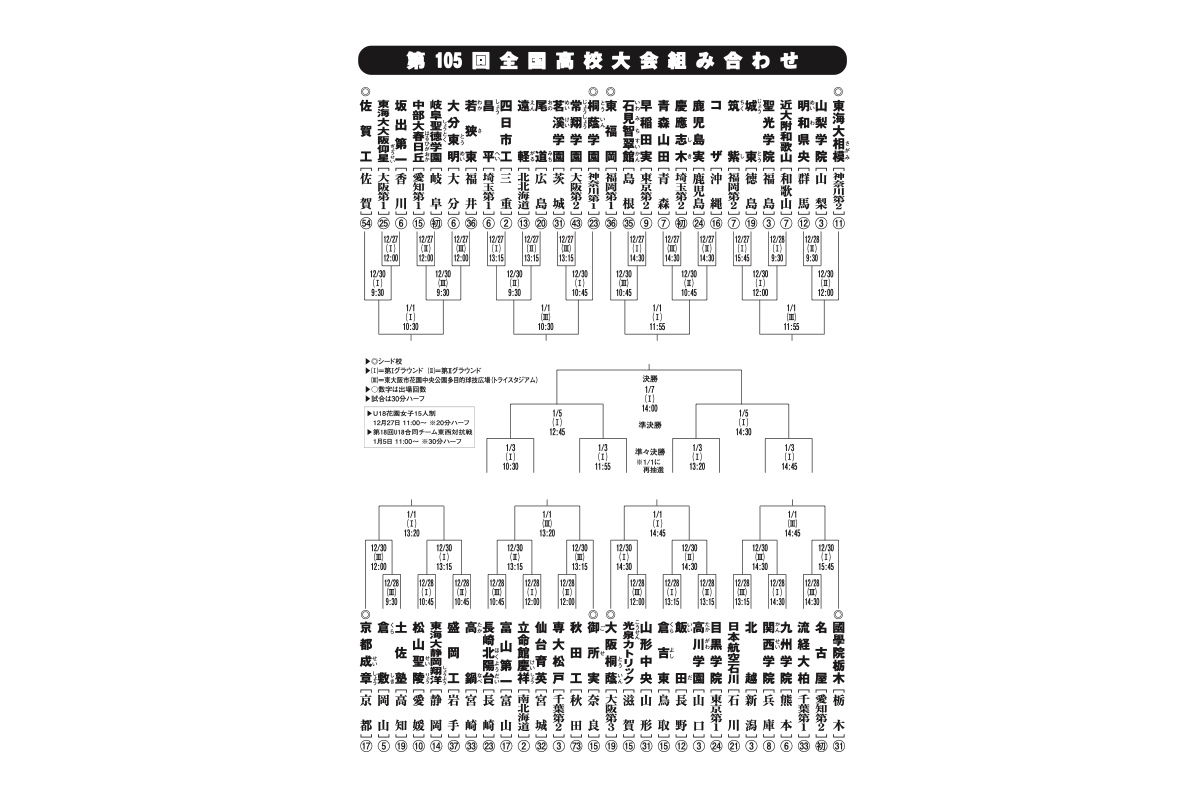子は育つ。3年後の玄祺と勇太。 田村一博(ラグビーマガジン編集長)

花園予選福岡県大会決勝。東福岡高校が修猷館高校を59-0で破った試合の記録用紙を見ていたら、懐かしい名前を見つけた。
崔玄祺(ちぇ・ひょんぎ)。勝者の側の7番に名前があった。3年生になって常勝チームのレギュラーに定着した。
彼が中学3年生だった1月に会った。3年経つのは早い。
2012年の1月に北九州に彼をたずねた。当時彼の書いた作文が、全国中学生人権作文コンテストで内閣総理大臣賞に選ばれたのがきっかけだった。そのことを日本ラグビー協会の森喜朗会長が花園の開会式で話した。閉会式でもくり返し紹介したのは、そのときの大会で優勝した東福岡高校のメンバーに、玄祺の兄、凌也(るんや/現・筑波大2年)がいたからだった。
帆柱ヤングラガーズでラグビーをプレーし、九州朝鮮中高級学校に通っていた玄祺は、取材で会う直前、父に「東福岡高校へ行かせてください」と伝えていた。福岡県中学校選抜のメンバーとして花園でプレーしたことはある。しかし、今回の花園出場は格別の思いだろう。チーム内での競争。県内にひしめくライバル校との対戦。それらを経て、夢の舞台に立てるのだから。
先日、久しぶりに電話で話した。
「(花園出場が決まった瞬間は)本当にうれしかったです」
「ラグビー部の仲間と馬鹿やっているときがいちばん楽しい」
お母さんの英(えい)さんとも話す。
「幼い頃から、アフリカの水をキレイにして、住んでいる人たちに飲ませてあげたい、というようなことを言っていたんです。人道支援に関連したことを仕事にしたいという思いで、進学先も決めたようです」
青山学院大学国際政治学部へ進むそうだ。
「例えばラグビーを通して、日本で使わなくなったジャージーやスパイクを集めてアフリカに送るとか、そういった活動をやっていきたいんです」(玄祺)
どうしてそのようなマインドを持つようになったか、自分自身もわからないと言った。使命感とは違う。持って生まれた性格か。以前のお母さんの言葉を思い出した。三兄弟の中の二男のことを「男気がある」と言っていた。
玄祺は、自然体で人に手を差しのべられる人間。ラグビーをやるために生まれてきた。FLにうってつけの男だ。
彼が当時書いた作文は、友人の森勇太について思いを綴ったものだった。勇太は帆柱ヤングラガーズの仲間。先天性四肢障害で生まれながら右手の手首より先がなく(右手尺骨欠損)、右足の指にも障害があった。幼い頃は乗馬やバドミントンなど、なんとかひとりでやれるスポーツを勧められ、それらに取り組んでいた。でも小学5年生になって、双子の兄が小学2年生からやったラグビーの世界に自分も加わる。3年前に会ったとき勇太は、当時の気持ちを「羨ましかったんです、兄が。みんなと練習して、みんなと喜んで。楽しそうだったから、僕も前からやりたかった」と教えてくれた。
玄祺の作文は、障害のある勇太に対して、周囲の大人たちがすぐに「ちゃんと全員でフォローしてやらんね」とか「手伝ってあげんね」と言うことに対しての違和感を書いたものだった。
《以下作文から抜粋、要約》
『小学校の時から同じラグビースクールで共にプレーしてきた。(彼は)体も小さく、体重も軽いが、厳しく辛い練習に弱音も吐かず、寒い日も暑い日も一緒にラグビーボールを追いかけてきた。
自分で出来ることは自分でやる。ぼく達も、そんな彼を当たり前のように待つ。手が不自由だからと特別扱いなど決してしなかった。だからミスには遠慮なくダメ出しもするし、本気で言い合いになり最後はケンカになることもあった。彼は言い出したら引かない。小さな体で喰いついてくる。どんなに言い争うことがあっても、練習や試合が終われば、ぼくたちは笑顔に戻るのだ』
『頼みもしないのに、彼のやるべきことを先取りした時の、少し淋しそうな「ありがとう…」をぼくは知っている。大人達の心配も分かるが、ぼく達が必要以上に手助けすることは、彼を少しずつキズつけて、彼の居場所やすべきこと、そして生きる力をも奪っているようにしか思えないのだ。
ただ、このことを本人に面と向かってたずねたことはない。
でも、ぼくにはわかる気がする。共にグランドを走りまわり一つのボールを追いかけて、パスをつなぐと彼の考えていることが』
勇太にすぐに手を差し伸べてあげなさい。そう言われることへの違和感を、玄祺はこう語っていた。
「ひとりになったときに何もできなくなると思う。誰もいないと出来ないなら困ってしまう」
友の努力を知っていた。右手に障害があるから、そちら側で入るタックルが弱い。だから勇太は、いつもそこを何とか克服しようとしていた。
「何度もタックルマシーンに入っているのを見たことがあります。泣きながら練習していました」(玄祺)
自分で道を切り拓くことができる男だと知っていた。
玄祺の作文を読んだときの思いを、勇太はこう言ってクスッと笑っていた。
「俺のことよくわかってるな、と」
そして続けた。
「なんでいつも、そんなこと(周りの人たちは、何かをやってあげなさいと)言うんだろうと思っていました。僕だって、時間をかければひとりでやれる。以前は出来なかったことだって、いまは出来るようになってますから」
子どもたちのたくましさを感じたやりとりだった。
勇太も高校でラグビーを続けたそうだ。福岡県立中間高校に進学し、楕円球を追い続けた。
高校でもラグビーを。息子の思いを玄祺の作文で知った勇太の母は、当時こう語ってくれた。息子のラグビーは中学で終わり。続けて行くのは体も、心も無理と決めつけていた自分の思い違いに気づいた、と。
「私が決めることではないんだな、と。出来ないって勝手に決めていた。体を動かしたくて仕方がないんです、あの子は。親が勝手に、どこかでストップをかけてきた。口出しもしてきた。そんなこと、もうやめようと思いました」
そして勇太は、思いを貫いた。3年間やり遂げた。3人しかいなかった3年生の中の一人としてこの秋の花園予選にも出場。初戦の福岡西陵戦で敗れ(19-47)、その試合の途中に膝を負傷して無念の交代となったけれど、よき仲間に恵まれて、高校ラグビーを存分に楽しんだ。
父・法仁さんが、勇太が高校に入学したときのことを思い出す。
「先生からみんなに(障害があることを)言ってもらった方がいいんじゃないか、と考えたんですよ。でも思い過ごしでした。周囲の友だちはみんな当たり前のように受け入れてくれて、本人もどうってことない(笑)。いまは彼女もおるらしく、高校時代、楽しくやったようです。本当に、いつも仲間に恵まれました」
いろいろな報道で存在を広く知られていた勇太。対戦校の指導者たちも中間高校の背番号11に注目した。そして誰もが、その激しいタックルに驚いた。
門司学園でラグビー部を指導する阿部展裕さんが教えてくれた。
「春の九州大会予選は合同Aチームとして門司学園と中間高校で出場しました。細身ながら俊敏で、超ツメツメの足首タックル連発していました。
中間高校は私の恩師が監督をしている縁もあって、よく合同練習や練習試合をおこなっています。合宿も一緒です。だから、彼を1年生のときから見ています。アタックでもディフェンスでも俊敏な動きとラグビーに対する熱い気持ちを感じる選手です。タックルは前述のとおり。アタックでも俊敏なステップや片手でのオフロードパス、倒されたときも丁寧なダウンボールをします。体のハンディと向き合いながら、彼なりの献身的なプレーを工夫して編み出してきたのだろうと感心します。おそらくジュニアの頃から基本的なプレーをしっかり練習してきたのだろうと思います。
合同チームのときは唯一の先発3年生BKでしたのでBKリーダーに任命して、他の経験値の浅い1・2年生BKを鼓舞してくれました。試合には1回戦で負けましたが、結果以上に彼のスピリッツから得るものがあったと思っています」
玄祺のお母さんも、勇太のお父さんも、嬉しそうに言った。
「子は育つ(笑)」
知らぬ間に、たくましく。楕円の世界に生きて、なお強く。
【筆者プロフィール】
田村一博(たむら・かずひろ)
1964年10月21日生まれ。89年4月、株式会社ベースボール・マガジン社入社。ラグビーマガジン編集部勤務=4年、週刊ベースボール編集部勤務=4年を経て、1997年からラグビーマガジン編集長。