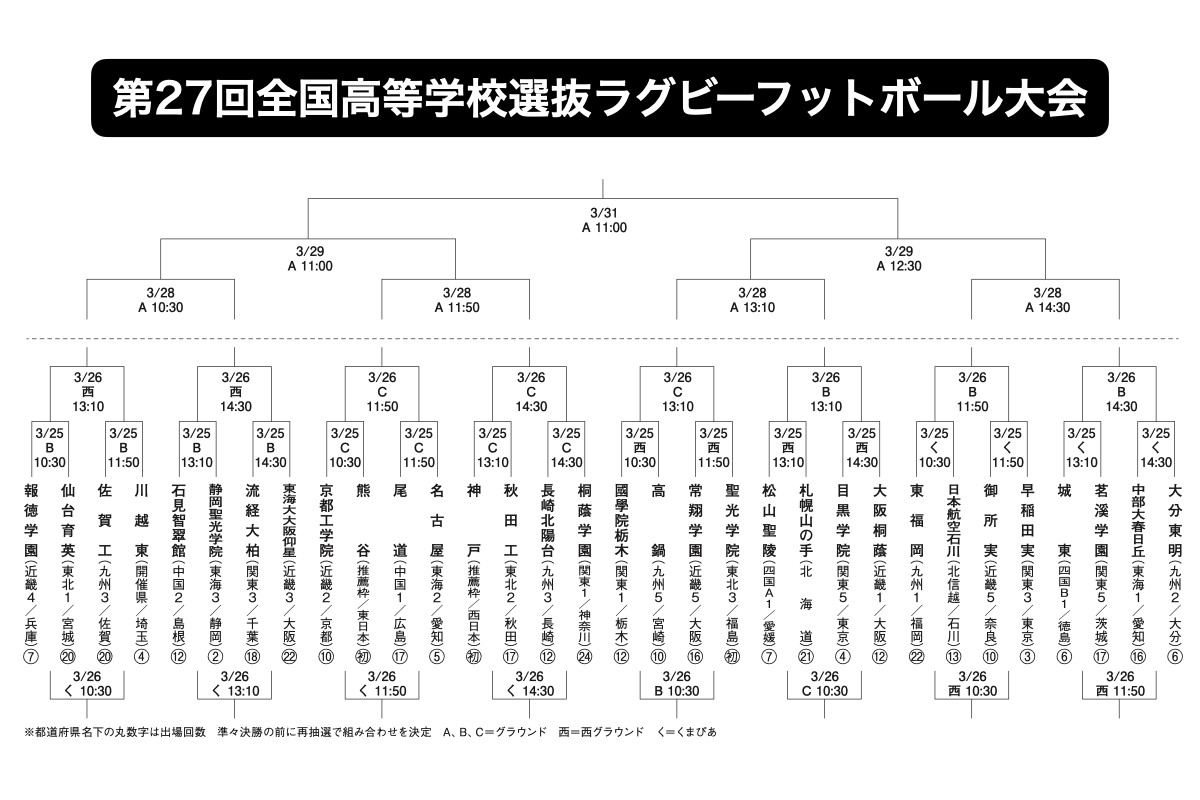コラム
2018.02.15
【直江光信 コラム】大変な時代。

■試合の緩急において、プレーヤーが気を抜くことのできる余地はどんどん狭まってきている。
トランジション。現代ラグビーにおけるもっとも重要なキーワードのひとつと言っていいだろう。直訳すれば「移り変わり」「転調」。不意のエラーやジャッカル、ペナルティなどで攻守が入れ替わったターンオーバー直後の、ポジショニングが乱れた状況への対応を意味する言葉だ。その混沌を制する側が主導権争いを制し、ひいては試合を制する。
ターンオーバーが起こった瞬間、それまで攻めていたチームは次のアタックを想定した陣形をとっており、守りの体勢にはなっていない。そこでボールを奪った側がすばやくディフェスの薄いエリアを攻めることができれば、ビッグチャンスになるのは必然だ。実際、試合を観戦しているとそうした場面を頻繁に目にするし、分析データでもターンオーバー時はトライが生まれやすいという明確な裏付けがある。組織ディフェンスが高度に発達し、ただ攻め続けるだけでは相手防御を崩せなくなっている昨今、トランジションの重要性はますます高まる一方だ。
そして先週末、シックス・ネーションズ第2節のイングランド対ウエールズの中継を見ていて、あらためてトランジションの意味について考えさせられた。どちらのチームも、何フェーズにも渡る相手の攻撃に窮地に追い詰められながら、ボールを奪うやいなや迷いなくパスをつないでアタックに転じる。自陣深くの地点からでも、疲労が蓄積する試合終盤になっても、その一貫した姿勢は揺るがなかった。
どれほど「ターンオーバー時は絶好のチャンス」とわかっていても、自軍ゴール前に長時間釘付けにされ、必死にタックルし続けてようやくボールを取り返した状況でアタックを仕掛けるのは、そう簡単ではない。「ひとまずはタッチに蹴り出して、ひと呼吸おいてから仕切り直そう」と思うのが普通だろう。ましてゲーム終盤となれば、疲れで味方の反応も遅れがちになる。一歩間違えば、せっかくターンオーバーしたのにふたたびピンチを招きかねない。
それでも、自陣ゴール前で安易にタッチに逃げる道を選択する気配は、イングランドにもウエールズにもまるでなかった。なぜか。そこには、単に「絶好の攻撃機会」というだけではないトランジションのとらえ方があるような気がしてならない。
敵陣深くまで攻め込み、ゴールラインに迫りながらトライを取れなかったら、そのチームは多かれ少なかれ気落ちする。試合展開がタイトになればなるほど落胆は大きいだろう。そこに「まさかここからは攻めてこないだろう」という意識が重なれば、集中力はたちまち緩む。そもそもあわててタッチに蹴り出したところでたいして陣地を戻せないし、ようやく危機をしのいだのに相手に休む時間と攻めるチャンスを与えることになる。それならすかさずカウンターアタックを仕掛け、一瞬たりとも気を休める時間を与えないほうがいい――。そんな強い意志が、両チームの戦いぶりに透けて見えた。
かつてのラグビーでは、タッチキックやペナルティでプレーが途切れれば選手も観客も一息つくことができた。しかしクイックスローやクイックタップで仕掛けるのが当たり前になった現在のラグビーでは、プレーヤーが気を抜くことのできる余地はどんどん狭まってきている。「休ませてもらえない」のだ。ホームのイングランドが12−6でウエールズを下した神経を削り合うような激闘は、そのことをひしひしと実感させた。
人間が忍耐力を持続できる時間には限界がある。肉体的のみならず精神的にもプレッシャーをかけ合い、その我慢比べに勝ったチームが、勝利を手にする。今のラグビーはそうした色合いが年々強くなっている。おそらくはフィジカルやスキル、戦術が成熟し、そうした部分で差をつけるのが難しくなったことで、メンタル面の勝負に占める比重が増えてきているのだろう。
国内シーンを振り返っても、その傾向は随所に表れていた。大学選手権決勝、帝京大学が自陣ゴール前のペナルティから明治大学の隙を突いてクイックタップで仕掛け、ほぼ100メートルを切り返して逆転を果たした後半20分のシーンは、トランジションへの高い意識もさることながら、強靭な精神力の賜物だった。東福岡、大阪桐蔭との死闘を制し、全国高校大会で頂点に立った東海大仰星のここ一番にかける気迫と集中力も見事だった。2017年度の国内最高峰を争う日本選手権兼トップリーグ総合順位トーナメントの決勝、サントリーとパナソニックが繰り広げた息つく暇もない80分は、ワールドカップのファイナルのような張り詰めた緊張感があった。
と、ここまで書いて、大変な時代になったなあとしみじみ思う。ゲームの強度が高くなれば、それだけ選手が受けるダメージも大きくなる。肉体面だけでなく精神面の負荷も考えれば、消耗の総量はいったいどれくらいになるのだろうか。
イングランド−ウエールズ戦を見ていて、「ここまでやって大丈夫なのか」と少し心配になった。近年は激しさを増すばかりのラグビーの未来に警鐘を鳴らす声が各方面から上がっている。シックス・ネーションズ全体を見渡しても、2節を終えた時点で各国ともケガ人が続出している。ラグビー界は今、大きな岐路に立たされているのかもしれない。
【筆者プロフィール】
直江光信(なおえ・みつのぶ)
スポーツライター。1975年熊本市生まれ。県立熊本高校を経て、早稲田大学商学部卒業。熊本高でラグビーを始め、3年時には花園に出場した。著書に『早稲田ラグビー 進化への闘争』(講談社)。現在、ラグビーマガジンを中心にフリーランスの記者として活動している。