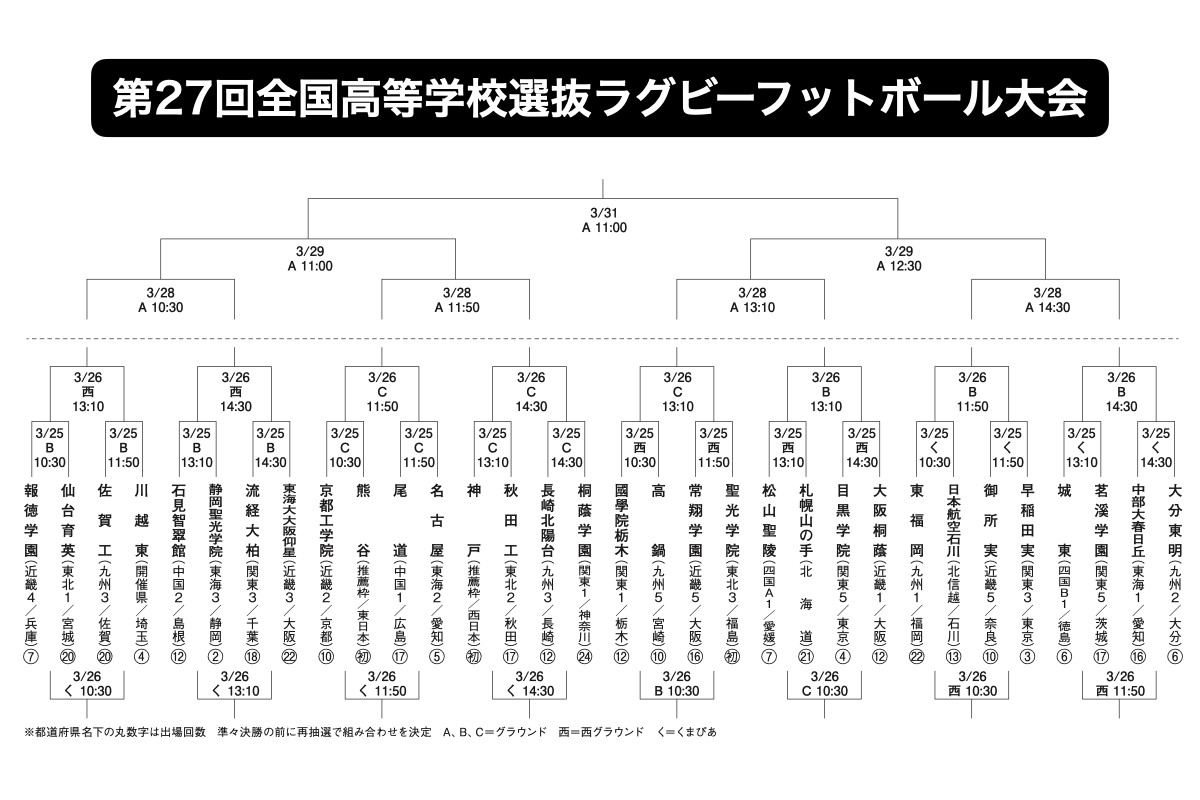【コラム】この土地を祝福し大地を護り給う
日本大会で初めてワールドカップに出る南アフリカ出身のフランカー、ピーター・ラブスカフニは、さざれ石を見て戦う大義を見つめ直したという。他国の逸話に、自軍のスタンスを重ね合わせる。
「日本国歌は私たちのやって来たことを含め、すべてを表している。小さな石が大きな岩になって、大きな役割を果たす。それは、まさに私たちがやろうとしていることです」
スポーツの代表戦において、「国歌」の時の顔つきや声色がチームの団結力の指標になっているのは確か。歴代もしくは現役のジャパン戦士が言い残してきた「勝つなら君が代を皆で…」という意志は、間違いなく尊重されるべきだ。市民が世界大会の開催国が出場国の「国歌」を覚え、来日した選手やファンを歓待するのも素敵な態度だ。
一方、そもそも人には歌を歌う自由も歌わない自由も、もちろん頭のなかだけで歌う自由もある。定められた「国歌」を国歌と認める自由も、認めない自由もまた。ちなみに日本で『君が代』が「国歌」と定められたのは、「国旗及び国歌に関する法律」が成立した1999年。歌ができてからずいぶんと経ってからのことだ。当時は『君が代』が戦時中の意思決定者を讃える内容と見られたことから、法案可決に反対する勢力もゼロではなかった。
話の流れから「国歌」への愛着と「愛国心」との関連性が気になる読者もおられるだろうが、愛の形が十人十色であるのは普遍的な真実だ。例えば、ぶっきらぼうながらクラス思いの青年が卒業式で校歌を歌わない(あるいは式に出席しない)という出来事は、決して珍しいことではなかったろう。
その市民が日本という国を愛しているのか、その選手が日本の代表チームのために真剣に戦おうとしているのかは、口元を覗き込んだだけではわかるはずもない。少なくとも、国を代表するトップアスリートが意を決しておこなう「国歌斉唱」を、施政者が市民へ強要するのはやや乱暴かもしれない。
いずれにせよ、これから始まる大舞台でラグビーマンを見るなら、口元の動きよりも心のありようを見たい。一見するとよくわからない、他者が決して侵すことのできない、心のありようだ。
9月6日、埼玉・熊谷ラグビー場。南アフリカ代表戦前のラブスカフニは、鋭い眼光をぐらつかせずに『君が代』を歌った。